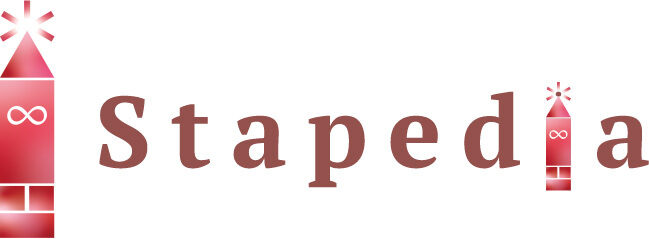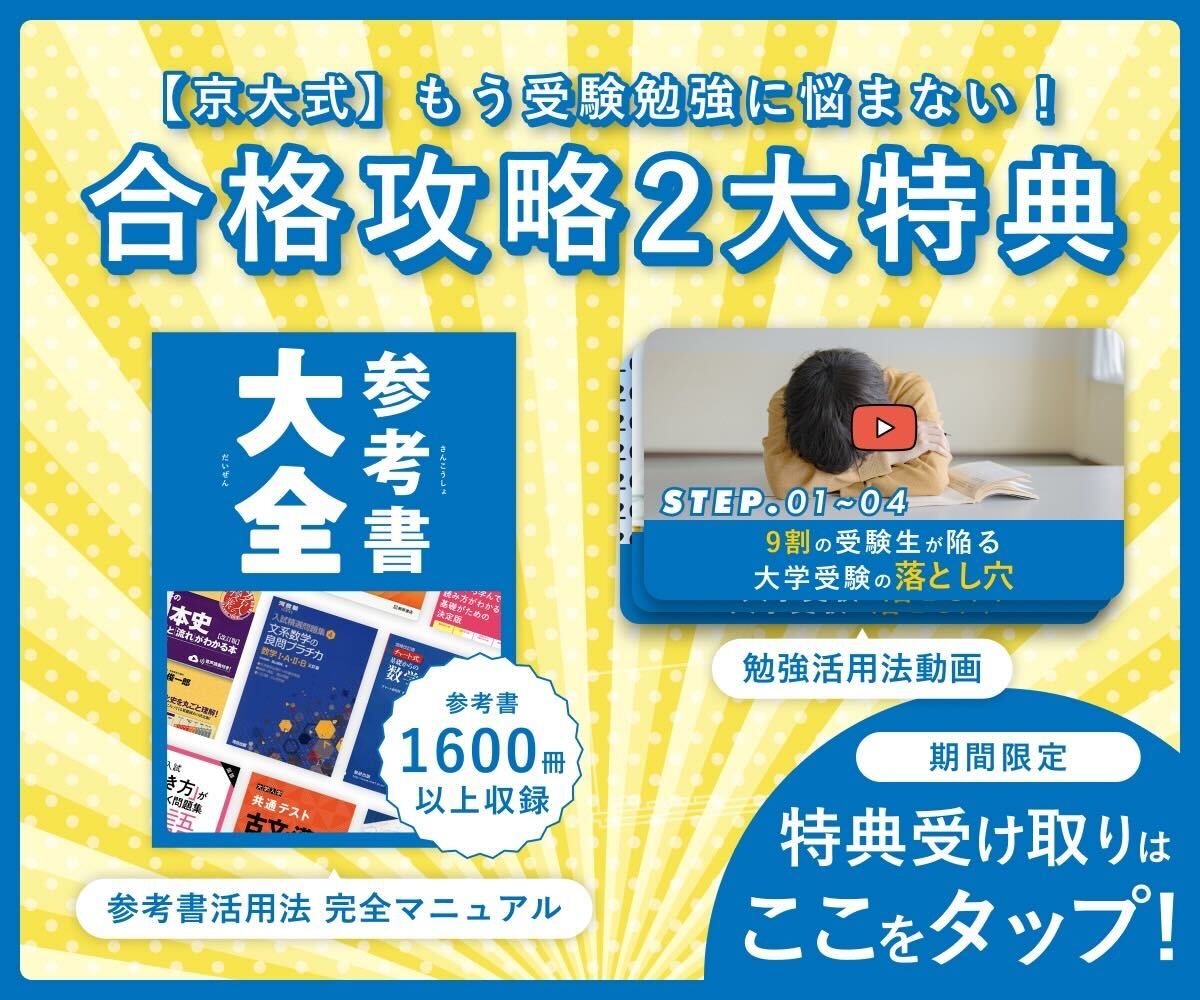こんにちは!スタペディアの巽です。
九大を目指す皆さんは「九大模試」を知っていますか?
大手予備校は各大学の受験生に向けて、二次試験に寄せて作成した実践形式の模試を実施しています。
これらを一般的に「冠模試」と呼びます。
冠模試の九州大学版が「九大模試」というわけです。
- 九大模試ってわざわざ受けた方がいいのかな?
- 九大模試を受けたいけど、どこの予備校の模試を受けるのが良いんだろう?
九大を志望している受験生の中には、このような疑問を抱いている人もいるでしょう。
今回は、九大模試に関して、2023年度の実施予定や予備校ごとの特徴から、受けるメリットやオススメの模試まで徹底的に解説していきます。
この記事を書いた人
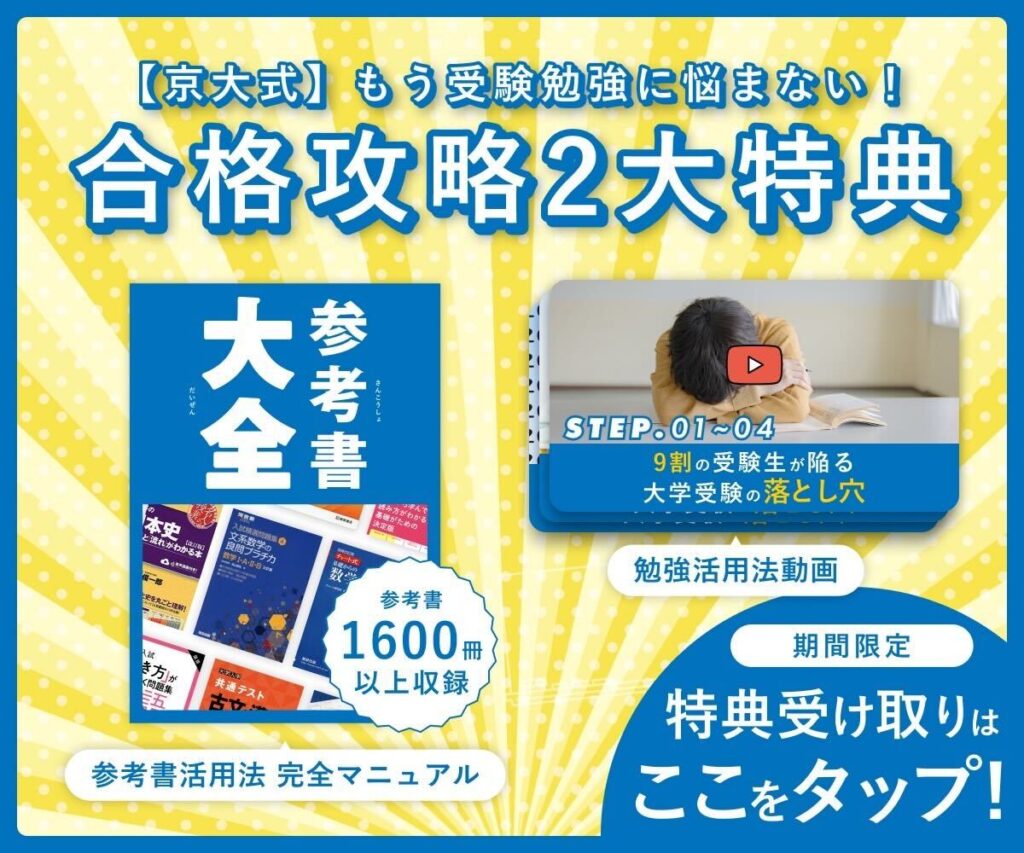
2023年度の九大模試の日程
九大模試は駿台・河合塾・東進・代ゼミの4つの予備校が実施しています。
2023年度の九大模試の日程は以下の通りです。
| 実施日程 | 模試 | 予備校 |
|---|---|---|
| 6/18(日) | 第1回九大本番レベル模試 | 東進 |
| 8/6(日) | 九大入試プレ | 代ゼミ |
| 8/6(日) | 第2回九大本番レベル模試 | 東進 |
| 10/1(日) | 第3回九大本番レベル模試 | 東進 |
| 10/22(日) | 九大入試実践模試 | 駿台 |
| 11/5(日) | 九大入試オープン | 河合塾 |
九大模試は受けるべき?受ける3つのメリット
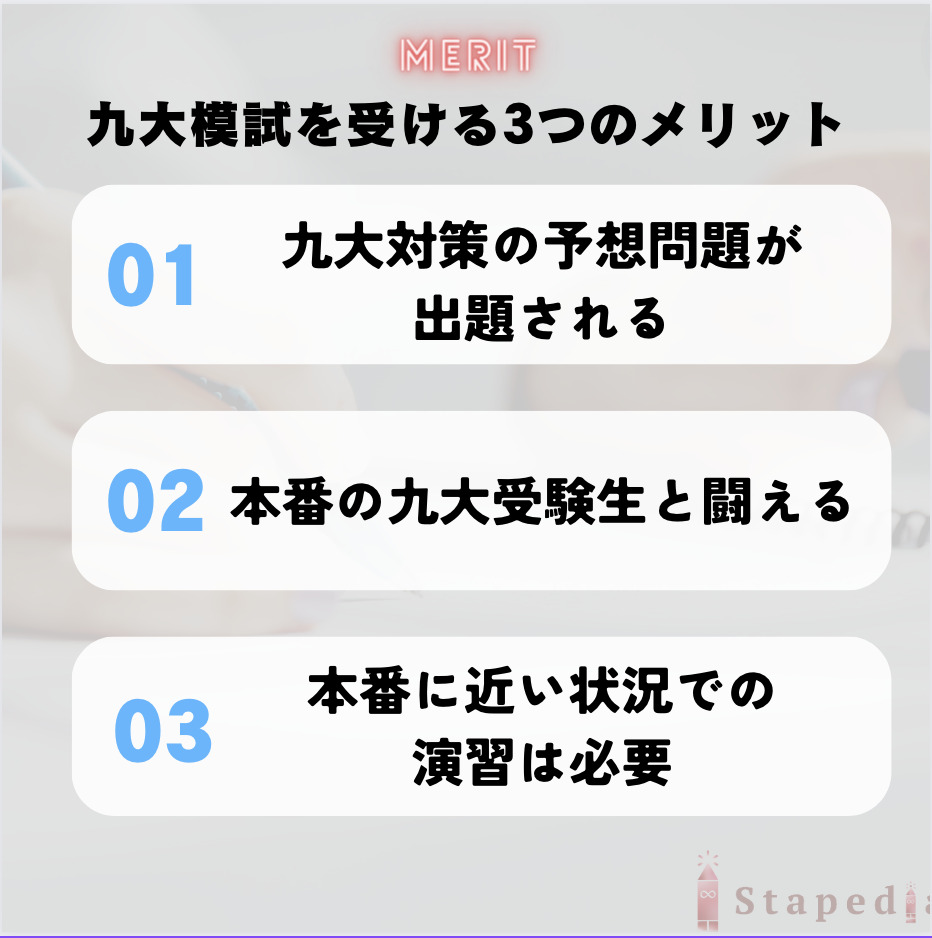
もしあなたが九大を受験するのであれば、九大模試は受けておくべきです。
九大受験生が九大模試を受けるべき理由は大きく3つあります。
- 九大対策の予想問題が出題される
- 本番の九大受験生と競える
- 本番に近い状況での演習は必要
九大対策の予想問題が出題される
九大模試を受ける最大のメリットは、九大の実際の試験に寄せた問題を解けることです。
もちろん過去問演習からもある程度九大入試のパターンや特徴は掴めるでしょう。
しかし、一度出た内容が同じ大学で再出題されることは考えにくいです。
九大模試であれば、大手の予備校が出題予想した内容を、九大の出題形式やパターンに当てはめた予想問題で実践演習が積めます。
例えば2022年度であれば、河合塾の「九大入試オープン」で「オーストラリアの民族問題について、白豪主義に触れながら記述する」問題が出題されました。
そして、九大入試でも同じ内容を記述させる問題が出題されたのです。
もちろんここまで的中する問題はそう多くありませんが、模試を完璧にしておけば本試での得点が伸びるのは間違いないですよ。
本番の九大受験生と闘える
また本番の九大受験生と闘えるのも、九大模試を受ける大きなメリットです。
九大模試であれば、受験者のほとんどが九大受験生なので、本番の受験生内での偏差値などがわかるのです。
今後の勉強計画を立てる上で、九大受験生の中でどのくらいのレベルにいるのかを知っておくことは非常に大切ですよ。
実践演習をすることに加えて、現在の立ち位置を把握することも、模試の大きな意義の一つです。
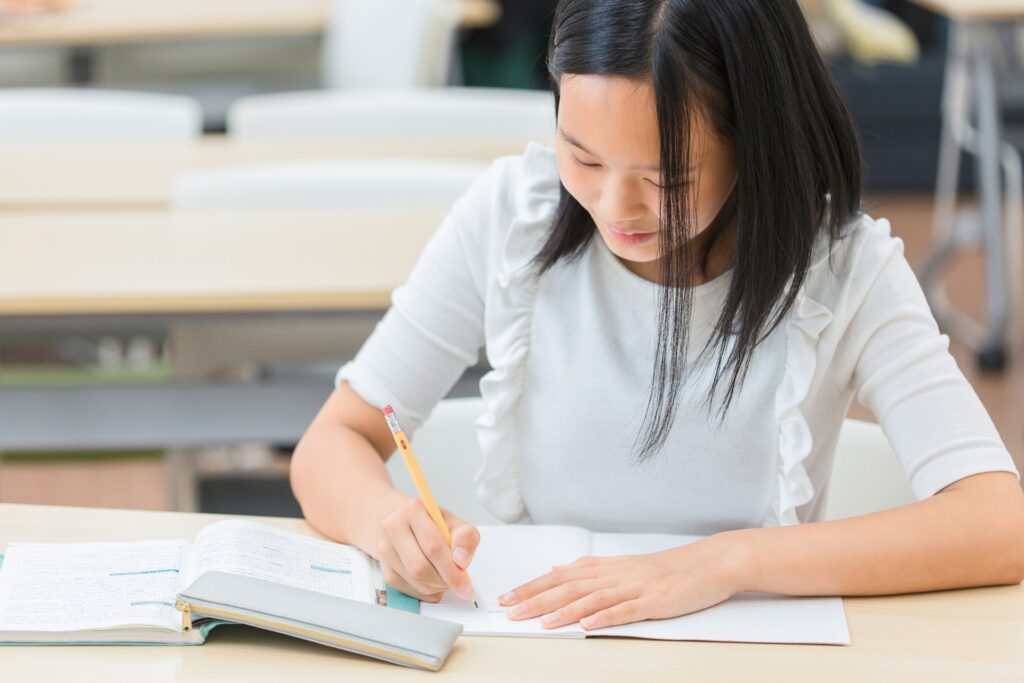
本番に近い状況での演習は必要
3つ目は、本番に近い状況での演習はやはり必要だからです。
これは特別九大模試に限ったことではありませんが、冠模試で前もって試験に慣れておいて、入試当日に緊張したり焦ったりしないようにしておくのは大切です。
また、調子によってどのくらい偏差値や判定が左右するのか、というのを知っておくのも重要です。
「過去問を家で時間を測って解けばいいじゃない?」と思っている人もいると思います。
実際、私も冠模試を受けるまではそう思っていました。
しかし、家での過去問演習と模試や本試での集中力や疲れがかなり違います。
下に少し私の経験談を紹介します。
私は京大の理系学部を志望していたのですが、京大の理系学部は数学が150分、理科が180分ととても長いんです。そのため、初めて京大模試を受けたときに、理科の途中で疲れて眠くなってしまいました。
そのとき、「自分は試験時間の180分を目一杯は使えない、途中で少し休憩を取らないと、頭が回らなくったりミスをしたりして、かえって点数が下がってしまう」ということを知ったのです。180分で解くように考えていた時間配分など、試験戦略を練り直すことにしました。
もしも、私が冠模試を受けずにいきなり本試に挑んでいたら、途中で疲れて眠くなり、試験どころではなかったことでしょう。
これは一例ですが、人それぞれ過去問の演習だけでは予想できない事態に陥ることもあると思います。このような意味でも本番に近い状況での演習は必要、というわけです。
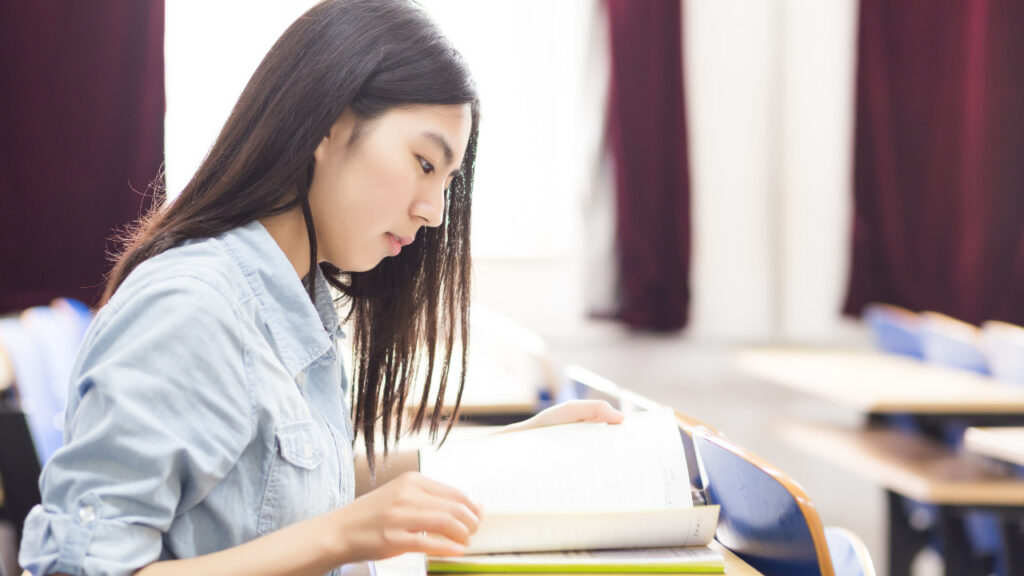
予備校ごとの模試の特徴
九大模試と言っても、予備校ごとに特徴があります。
今回は難易度順に紹介していきます。
駿台
| 実施日程 | 模試 |
|---|---|
| 10/22(日) | 九大入試実践模試 |
最も難易度が高いのが、駿台の「九大入試実践模試」です。
九大模試に限らず、駿台の模試は他の予備校の模試と比較すると、問題のレベルが高いです。個人的には、駿台の冠模試は実際の入試より難しいと思っています。
なので、しっかり復習して定着させれば、かなりの自信につながりますよ。
「駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試」も併せて受けると、ドッキング判定が行われて、より具体的な偏差値や判定が得られます。
詳細は駿台のHPをご覧ください。
河合塾
| 実施日程 | 模試 |
|---|---|
| 11/5(日) | 九大入試オープン |
河合塾の「九大入試オープン」が九大入試のレベルに一番近いです。
日程も本試の日程に近く、他の受験生も仕上がっているので、偏差値や判定はかなり信頼できます。
また、河合塾の九大模試は出題範囲予想の的中率が非常に高い点も魅力です。
直近だと、2023年の地理の記述問題が同じ題材についての記述問題が出題されたり、日本史で同じ人物名を答える問題が出題されたり、といった完璧っぷりです。
こちらは「全統共通テスト模試」とのドッキング判定が行われます。
詳細は河合塾のHPをご覧ください。
東進
| 実施日程 | 模試 |
|---|---|
| 6/18(日) | 第1回九大本番レベル模試 |
| 8/6(日) | 第2回九大本番レベル模試 |
| 10/1(日) | 第3回九大本番レベル模試 |
東進の「九大本番レベル模試」も、実際の九大入試とほぼ同程度の難易度です。
特徴は実施回数が3回と多いことです。
同じ予備校の模試であれば、受験者層も比較的同じと予想できるので、学力の推移を把握しやすいのがメリットになります。
詳細は東進のHPをご覧ください。
代ゼミ
| 実施日程 | 模試 |
|---|---|
| 8/6(日) | 九大入試プレ |
代ゼミの「九大入試プレ」は、実際の九大入試より少し簡単です。
なので、「九大志望だけどまだ本番レベルに到達していない…」という受験生にはオススメです。実施時期も夏なので、まだまだ本気で取り組めば間に合う時期です。
また、時期が駿台や河合塾より早めなので、一度早めに受けておきたい、と言う人にもオススメできます。
詳細は代ゼミのHPをご覧ください。
結局どこの予備校の模試を受けるべき?
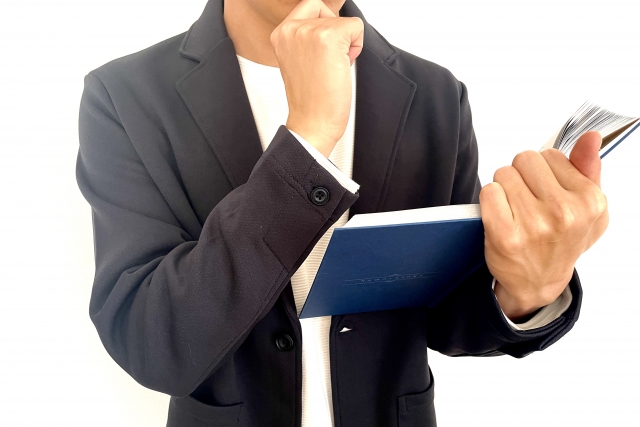
九大模試を受けるメリットや予備校ごとの模試の特徴を解説してきました。
それでは、結局どの模試を受けるのがよいのでしょうか?
必ず受けたいのは駿台と河合塾、少ないと思うなら代ゼミも
すべての九大受験生に受けてもらいたいのは、駿台の「九大入試実践模試」と河合塾の「九大入試オープン」です。
駿台は問題のレベルが高く、発展的な内容まで問われるので、実力をつけるのに最適です。
駿台の模試レベルを解ければ、九大の入試で大きく点数を落とすことは少ないでしょう。
河合塾は問題のレベル、予想問題の的中率共に一番本試に近い模試と言って良いので、偏差値や判定、試験戦略をチェックするためにも、必ず受けてもらいたいです。
一つ注意したいのは、駿台と河合塾は間が2週間しかなく、かなり力を入れて復習をしなければ間に合わないです。頑張りましょう。
ここからは、「2つだと少し不安だな…」という人向けで、特別オススメはしません。
東進の「第2回九大本番レベル模試」と代ゼミの「九大入試プレ」は日程が被っているので、両方は受けられません。受けるのであればどちらかの予備校に絞りましょう。
この2つであれば個人的には代ゼミの「九大入試プレ」の方が良いと思っています。
東進は3回とも受けないと効果が半減してしまいますが、たくさん受けるというのはそれだけ復習に時間が取られてしまうということです。
基本的には駿台と河合塾の2回、もしくは代ゼミを加えた3回受けるのをオススメします。
どの模試を受けるかは早めに決めておく
九大模試に限ったことではありませんが、どの模試を受けるのかは早めに決めて、日程は把握しておくべきです。
なぜなら、模試に合わせて勉強計画を立てないと受ける意味がなくなってしまうからです。
せっかく模試を受けるのであれば、次の模試までに復習を終わらせて、間違えた箇所を定着させておきましょう。同じ間違いを何度もしているようでは、もったいないですし、正しい偏差値や判定が出ません。
「復習なんて模試の後にすればすぐ終わるじゃん」と思う人もいるかもしれませんが、模試は一回復習して終わりではありません。
一度復習して完璧になるような問題を間違えているなら、それは単なる勉強不足です。
模試の復習が終わった、という人に同じ模試を解かせたとしても、満点近く取れる人は意外と少ないです。復習してその場では理解できても、きちんと定着していないのです。
これでは予想問題と同じ問題が出ても、同じ間違いをするだけです。
一度模試で間違えた箇所は定着できるまで何度も復習しましょうね。