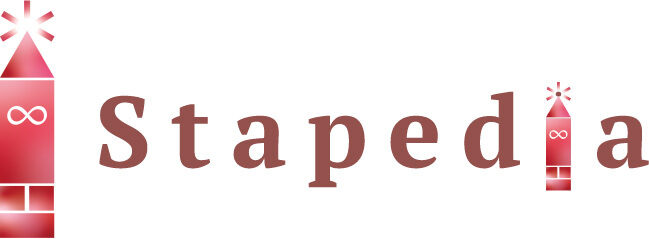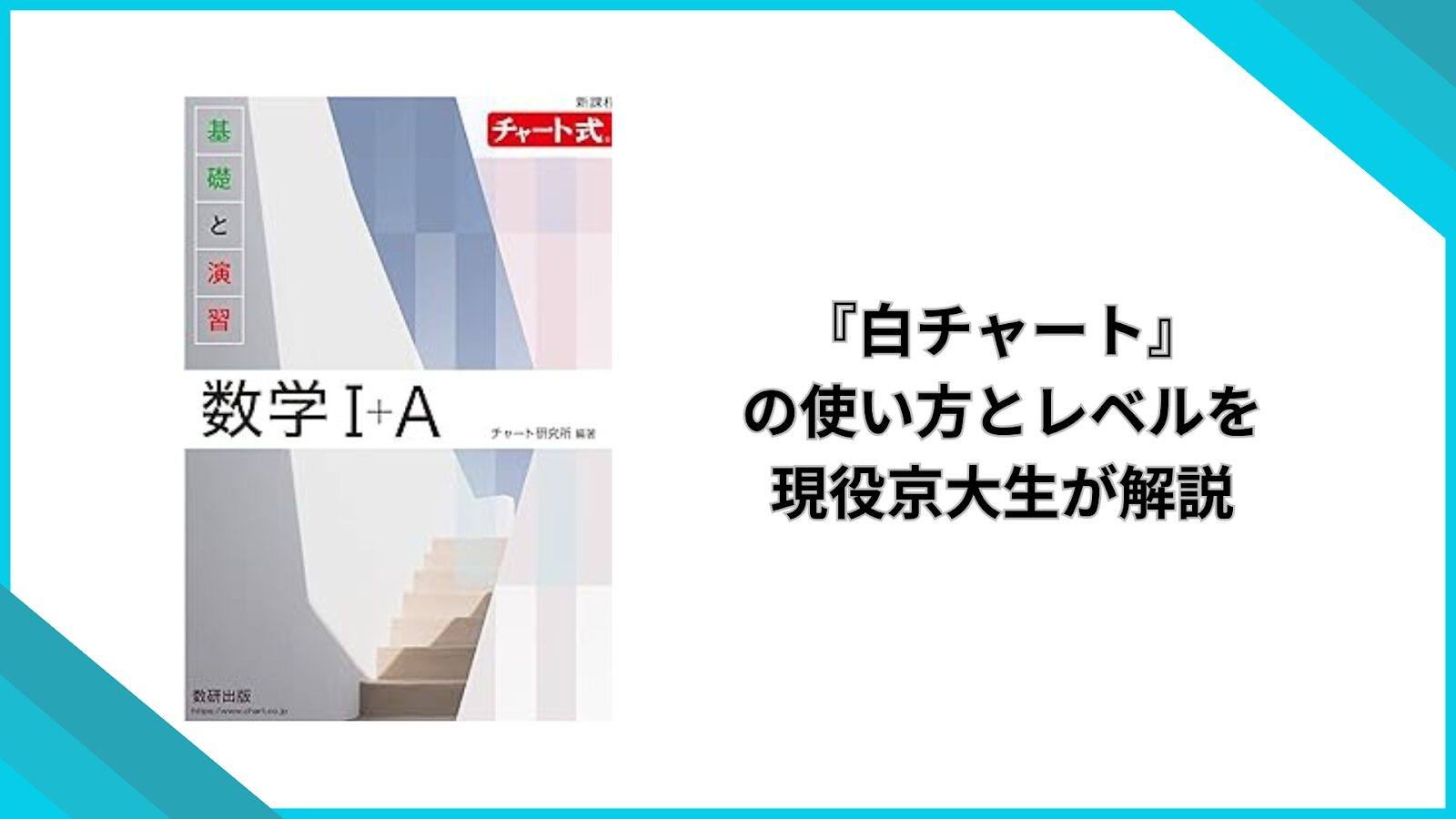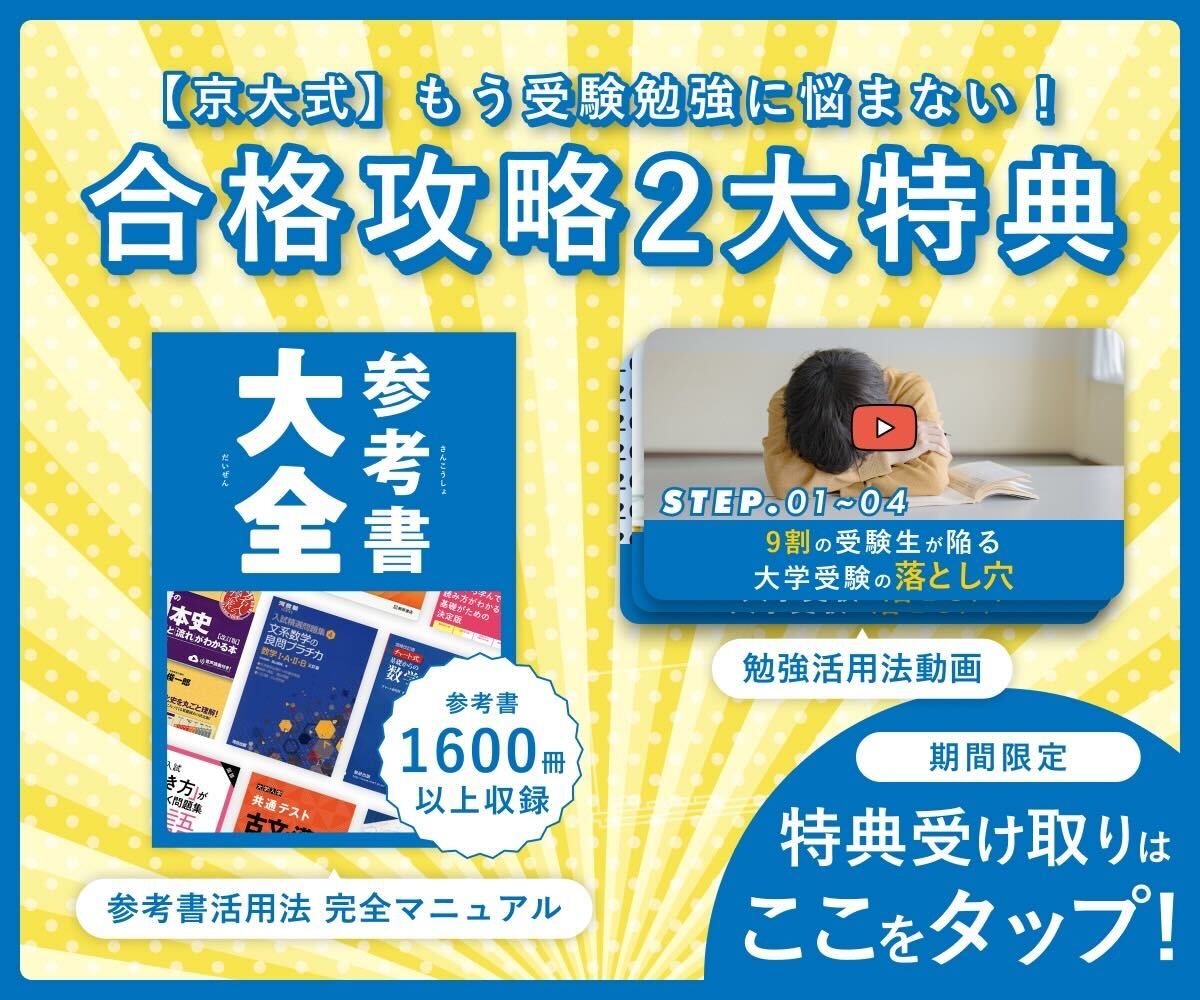『白チャート』は数研出版が出版している網羅系の参考書で、数学の基礎を固めたい人におすすめの参考書です。大学入試の数学において知っておきたい基本的な解法が網羅的に収録されており、共通テストレベルの数学ならこの1冊を極めれば解けるようになります。
ただ、世の中にはたくさんの数学の参考書があり、『白チャート』が自分の志望大学のレベルに合っているのか、効果的な使い方ができているのか知るのは難しいですよね。
この記事では、『白チャート』の難易度や効果的な使い方、よくある質問などを解説していきます。本書の具体的な内容や難易度を理解して、適切に参考書を選べるようにしましょう。
この記事を書いた人
白チャートの商品情報
『白チャート』の商品情報です。
| 価格 | 数学I+A:1,881円数学II+B:1,991円数学III+C:1,892円 |
| 科目 | 数学 |
| 問題数 | 数学I+A:913題数学II+B:1116題数学III+C:不明(376ページ) |
| 出版社 | 数研出版 |
| 目的 | 大学入試数学の基礎力を身につける |
| 対象ユーザー | 共通テストで数学を使う受験生 |
| レベル | 〜日東駒専 |
| 難易度 | やや簡単〜普通 |
| 特徴 | 共通テストに対応するために必要な解法が多数収録されています。 |
白チャートのレベル・到達できる偏差値
本書は「日東駒専レベル」で、偏差値60・共通テスト数学7割程度まで到達できます。問題のレベルは他のチャート式と比較するとそれほど高くなく、数学が苦手な方におすすめの参考書です。
以下、本書に取り組むべき時期を志望校別に解説していきます。
・日東駒専:高3の4月
・GMARCH:高2の10月〜12月
・難関大(早慶・旧帝国大学など):高2の4月〜10月
・最難関大(東大・京大など):高2の4月〜6月
白チャートの強み
ここからは『白チャート』について、他の参考書と比較した強みを解説していきます。
網羅的に問題が掲載されている
本書の最大の特徴は、教科書レベルの問題から入試標準レベルの問題まで網羅的に問題が収録されていることです。幅広い難易度の問題が収録されつつも、入試でよく使う解法が厳選されて掲載されており、欠点がほとんど見当たらない参考書だといえます。収録されている問題ごとにレベルが掲載されており重要度がわかりやすくなっています。
定期テスト対策専用の問題がある
白チャートには「定期試験対策演習コーナー」があり、定期テストで出題されるような基礎的な問題を実戦形式で演習することができます。他のチャート式シリーズには収録されておらず、基礎的である『白チャート』ならではの魅力です。
解説がわかりやすい
解説がとてもわかりやすいことも大きな強みです。通常、網羅的な参考書は問題に多くの分量を割き、解説がおろそかになりがちです。しかし、本書は1問ごとに詳しい解答・解説がついており、数学力を最大限高めてくれます。
白チャートの弱み
ここからは『白チャート』について、他の参考書と比較した弱みを解説していきます。
分量が多く、挫折する可能性がある
チャート式シリーズすべてに言えることですが、「網羅系の参考書かつ解説が詳しい」ことで、非常に分量が多くなっています。特に数2Bは例題だけでも319題もの分量があります。そのような分量の多さに負けて、途中で挫折してしまう方も少なくありません。本書に取り組むにあたっては、事前に計画を練っておき、確実に実行できるようにしましょう。
白チャートの使い方
ここからは『白チャート』の効果的な使い方を解説します。
STEP1:1周目で問題を解き、解法をインプットする
『白チャート』を使用する際には、1周目はまず解法をインプットすることに努めましょう。以下のような手順でインプットすると効果的に学習できます。
①例題を見て、解法が思いつかなかったらすぐに解答を見る(解法がわかった場合は解いてみる)
②解法が思いつかなかった場合は節末のExercisesを解いてみる(解法がわかった場合は解かずに次の例題に移る)
③わかった問題には⚪︎、わからなかった問題には×をつけ、復習がしやすいようにする
STEP2:2,3周目で解けなかった問題を復習する
まず1周が終わったら、1周目で×をつけた問題をもう一度解いていきましょう。その問題が解けるようになったら、上から⚪︎をつけ、7〜8割が⚪︎になるまで復習を繰り返してください。何度も繰り返し学習するにつれて、自分の苦手な分野がわかってくるはずです。7〜8割が⚪︎になった分野についてはSTEP3に移行しましょう。
STEP3:解法がインプットできれば、章末のExercisesに取り組む
STEP2を終えたら、次は章末のExercisesにも取り組みましょう。日東駒専志望の方はここまで取り組む必要はありません。例題や節末のExercisesが完璧になるまで繰り返し問題を解くか、後述の「黄チャートの後におすすめの参考書」に取り組むのがおすすめです。
白チャートで1問にかける時間
例題は5〜10分、節末のExercisesは10〜15分、章末のExercisesの問題は20〜30分を目安に解くようにしましょう。特に節末のExercisesはその上の例題を理解していれば簡単に解ける問題が多いです。すぐに解法が浮かばなかった場合は例題を理解できていないということです。そのため5分考えてわからなかった場合は例題に立ち返って復習するようにしましょう。
白チャートに関する注意点
ここからは『白チャート』を使用する際の注意点を解説していきます。
教科書を7割程度理解していない方には難しい
『白チャート』は基礎から解説されていますが、教科書を7割程度理解していないと難しい問題が多いです。公式や基礎的な定理をある程度覚えている前提で解説が進められるため、まずは学校の復習をきちんと行い、7割程度理解してから本書で演習を積むようにしましょう。
難関大学の入試には対応できない
また、白チャートでは旧帝国大学などの難関大学の入試には対応できないことに注意が必要です。本書では、章末のExercisesは日東駒専レベルの問題が収録されています。難関大学を志望する方は、もう1冊アウトプット用の参考書を併用する必要があります。おすすめの参考書は「白チャートの後におすすめの参考書」で紹介しているので参考にしてみてください。
分量が多く、完成までに時間がかかる
白チャートは網羅系の参考書で、非常にボリュームが多い参考書になっています。特に数1Aは672ページもの分量があるため、完成までに長い時間がかかります。どれだけ短くても、1冊完成させるのに4〜5ヶ月はかかると考えておきましょう。
白チャートの前におすすめの参考書
ここからは『白チャート』を使用する前におすすめの参考書を紹介していきます。
数学 入門問題精講
教科書や学校の授業でもついていけないという人におすすめの参考書です。単元ごとの考え方や公式などが詳しく解説されており、数学嫌いの方や数学が苦手な方でも取り組みやすくなっています。初学者の方でも取り組みやすいですが、本書はあくまでも「入門」の参考書ということに注意してください。この参考書が終わり次第、『白チャート』や、その他の網羅系の参考書に取り掛かりましょう。
やさしい高校数学
『やさしい高校数学』は教科書レベルの基礎的な問題をわかりやすく解説している参考書です。そのため、数学が苦手な人や初学者でも取り組みやすくなっています。登場人物が会話する形式となっており、読み物としてスラスラ読めるため、わかりやすい参考書を求める方には最適です。
白チャートの後ににおすすめの参考書
ここからは『白チャート』を使用した後におすすめの参考書を紹介していきます。
数学 基礎問題精講
『白チャート』と同じ網羅系の参考書ですが、本書のほうが分量が少なく、少ない時間で基礎を固めることができます。白チャートを7〜8割理解してから本書に取り組むと、本書にも楽に取り掛かれます。入試基礎〜標準レベルの問題が収録されているので、日東駒専志望の方には特におすすめです。
数学 標準問題精講
本書は中堅私立・国公立を志望する方が『白チャート』の後に取り組むべき参考書です。中堅私立・国公立レベルの問題が多数収録されており、問題演習を通じて実戦力を磨くことができます。白チャートでのインプットが7割程度終了した後に取り掛かると効果的です。
1対1対応の演習
上位国公立大を目指す方におすすめなのがこの『1対1対応の演習』です。その名前の通り、例題1つに対して演習問題が1つという構成になっています。本書は扱っている問題が絞られており、白チャートなどの網羅系の参考書を終えた後に取り組むと、重要なポイントだけをおさらいできるため効果的です。本書に取り組んでみて、理解できない問題は白チャートに取り組んで復習すれば、より深い学びに繋がります。上位国公立大を目指す方はアウトプット用に、難関大学を志望する方はインプット用に取り組んでみましょう。
白チャートについてのよくある質問
ここからは『白チャート』について、よくある質問に答えていきます。
白チャートが終わったら、黄チャート、青チャートのどちらに移行するのがおすすめですか?
白チャート終了後は『青チャート』に移行するのがおすすめです。以下で白・黄・青チャートのレベルを解説します。
①白チャート:教科書レベル〜入試基礎レベル
②黄チャート:教科書レベル〜入試標準レベル
③青チャート:入試基礎レベル〜入試応用レベル
上記のように、白チャートと黄チャートはレベルの重複が大きいです。チャート式は前述の通り分量が多いため、白・黄の2つに取り組むと、重複した学習が多くなってしまいます。そのため、重複を減らし、効率的に学習するためにも、白チャートの後は青チャートに取り組むのがおすすめです。なお、難易度の観点から、日東駒専・GMARCHを目指す方は白チャートから青チャートに進む必要はありません。前述の「白チャートの後におすすめの参考書」に取り組むようにしましょう。
他の色のチャート式との違いを教えてください。
チャート式には、「白、黄、青、赤、緑、紫」の6つのシリーズがあります。それぞれの色の特徴を解説していきます。
・白チャート
基礎的な問題が多い。数学が苦手な人におすすめ。
・黄チャート
数学な苦手な人、中堅私立や中堅国公立を目指す方におすすめ。
・青チャート
一番標準的な参考書。実戦的な問題も多く収録されており、最難関大入試にも対応できる。
・赤チャート
チャート式で最も難易度が高い。東大や京大を目指す方や、河合塾の模試で数学偏差値65以上取れる方におすすめ。
・緑チャート
共通テスト演習のみに的を絞った参考書。
・紫チャート
入試で頻出の問題だけを収録している参考書。定期テストで点が取れるのに、模試では思うように点が取れない方におすすめ。