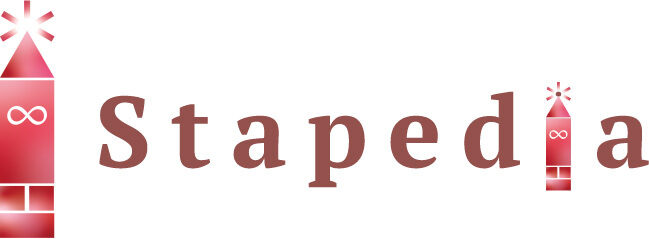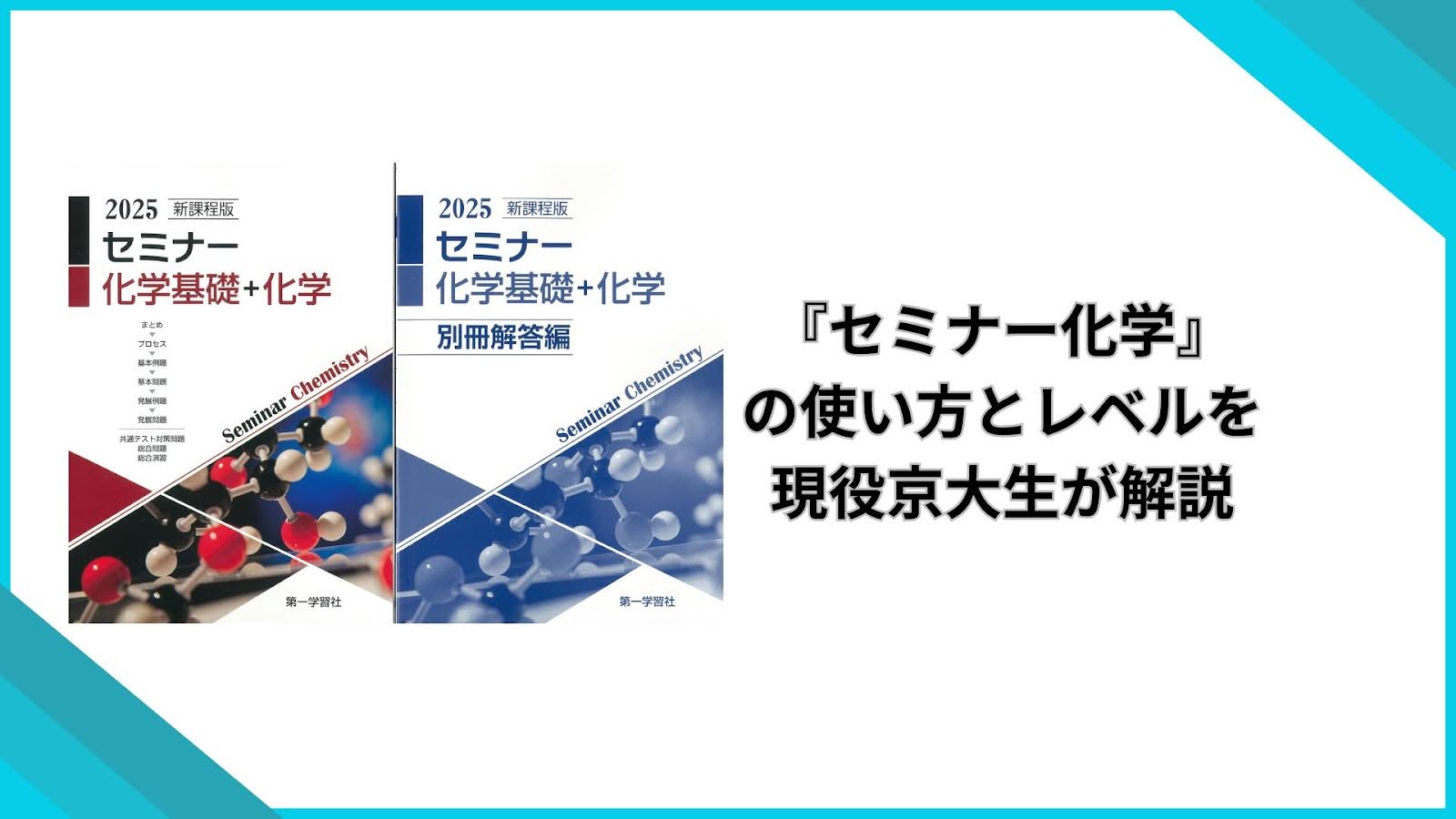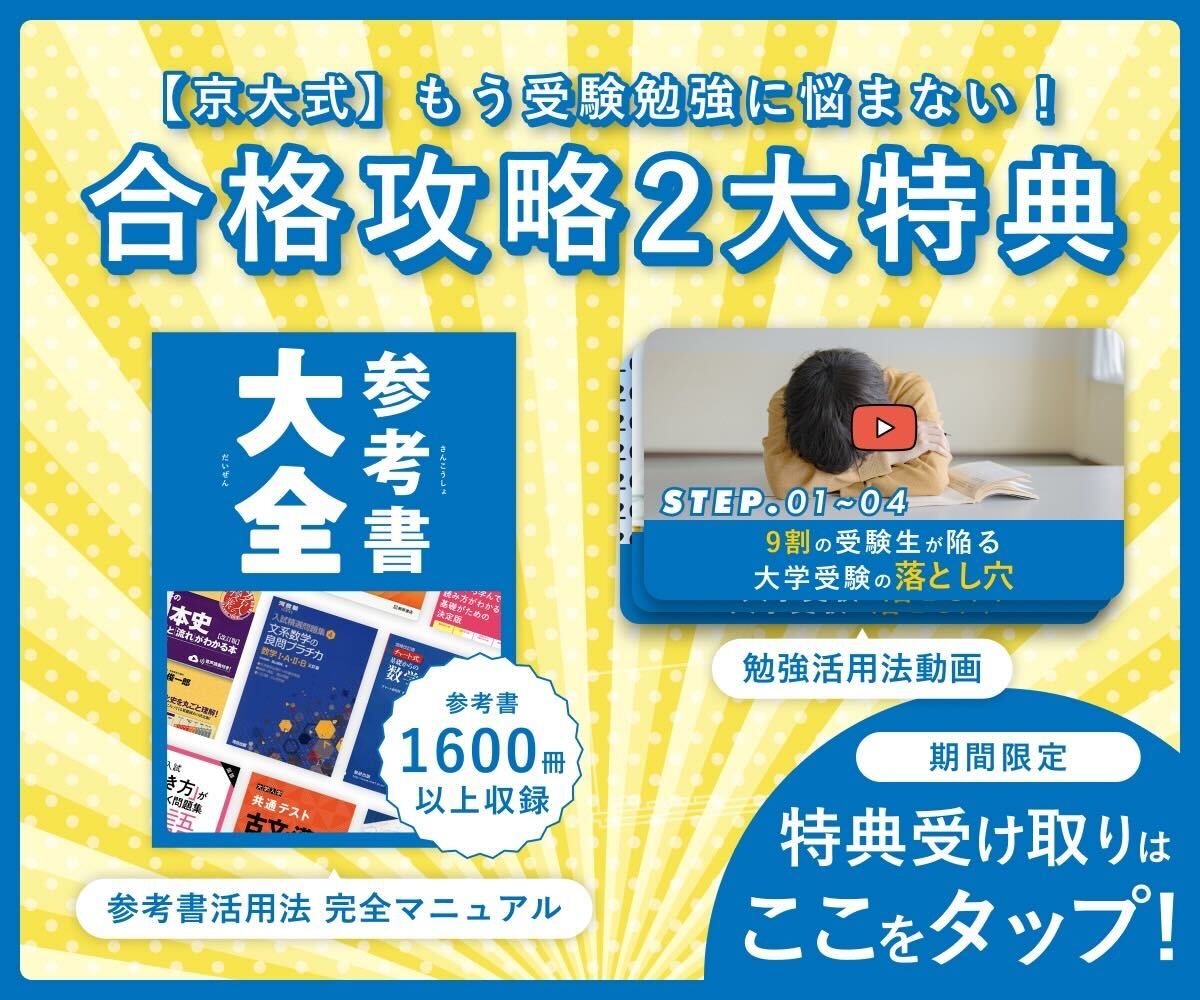『セミナー化学』は、第一学習社が出版している化学の網羅系問題集です。
化学の基礎的な範囲が網羅的に収録されており、「プロセス」や「ドリル」といった簡単な計算問題や知識確認問題を通して、化学を基礎の基礎から学べます。
ただ、『セミナー化学』が自分の学力レベルに本当にあっているのか、どのように進めると学習効果が高いのかを見極めるのは難しいですよね。
この記事では、『セミナー化学』の問題の難易度や解説の詳しい内容、効果的な使い方などを解説します。本の具体的な内容や問題の難易度を理解して、適切な参考書選びができるようになることを目指しましょう。
この記事を書いた人
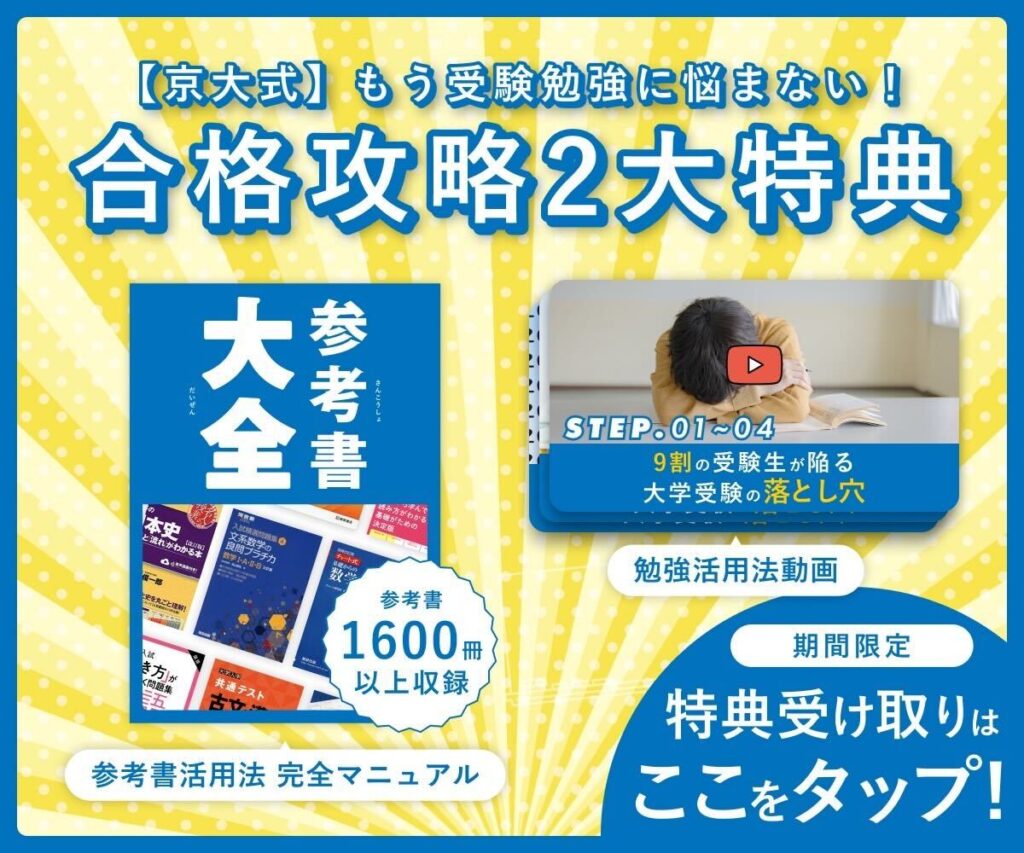
『セミナー化学』の商品情報
『セミナー化学』の基本情報です。
| 価格 | 1,045円 |
| 科目 | 化学 |
| 問題数 | 1,027題 |
| 出版社 | 第一学習社 |
| 目的 | 高校化学の基礎学力を養成する |
| 対象ユーザー | 入試で化学を使う全ての受験生 |
| レベル | GMARCHや地方国公立 |
| 難易度 | やや簡単〜普通 |
| 特徴 | 本書は、教科書と対応した構成で、基礎の基礎から網羅的に学べるという強みがある一方で、問題数が多すぎるので時間がかかり、応用問題の分量が少ないことが弱みとしてあげられます。 |
『セミナー化学』のレベル・到達できる偏差値
本書は、中堅国公立やGMARCHレベルです。本書を極めることで、入試基礎〜入試標準レベルの問題まで解けるようになり、偏差値62.5〜65まで到達できます。
そのため、早慶や旧帝大などのよりレベルの高い大学を目指す人は早期に完成させるべきでしょう。志望校のレベル別におすすめの学習時期を以下に記載しているので、参考にしてみてください。
- 産近甲龍、日東駒専:高校3年の10月
- 関関同立、GMARCH:高校3年の7〜8月
- 早慶、旧帝大:高校2年の3月
- 東京一工:高校2年の12〜1月
『セミナー化学』の強み
『セミナー化学』を他の参考書と比べた強みを紹介していきます。
入試に必要な範囲全てに対応できる
本書の最大の強みは、教科書の範囲を網羅していることです。教科書傍用問題集にも指定されており、高校化学の重要事項がもれなく収録されています。
さらに、大学入試では教科書の範囲以外からは出題されないので、本書を極めることで入試に必要な範囲全てに対応できるようになるでしょう。
基礎の基礎から学べる
高校化学を基礎の基礎から学べるのも本書の強みの一つです。例えば、「プロセス」では基本的な知識や原理原則から一問一答形式で学べ、基礎知識の確認に役立つでしょう。
化学は、他教科と比べて特に基礎知識や公式の理解が重要な科目です。入試に出てくる物質の化学式やその反応式がわからないようでは、より発展的な入試問題など解けるはずがありません。
本書を通して、土台となる基礎をガチガチに固めることで、スムーズに学力を向上させていけるでしょう。
教科書に対応するように構成されている
教科書と対応するように構成されているのも本書の強みと言えるでしょう。教科書傍用問題集であるだけに、学校の授業進度に合わせて学習できるように構成されています。
具体的には、各単元について「まとめ」→「プロセス」→「ドリル」→「基本例題/基本問題」→「発展例題/発展問題」と難易度が細かく分けられており、段階的にレベルを上げながら学習できるでしょう。
『セミナー化学』の弱み
『セミナー化学』を他参考書と比べた弱みを紹介していきます。
問題数が多すぎる
本書の最大の弱みとして、問題数が多すぎることが挙げられます。「プロセス」や「ドリル」などの簡単な問題をのぞいても600題以上収録されており、全ての問題をじっくりやるのは現実的ではありません。
できるだけ早い時期から取り組むだけでなく、2〜3周目は苦手な範囲に絞って進めるのが必要でしょう。
基礎が十分身についている単元では、基本問題を飛ばし気味にして発展問題から取り組んだりするなどの問題の取捨選択をしながら進めていけると良いです。
応用問題の量が少ない
応用問題の量が少ないのも本書の弱みと言えるでしょう。教科書レベルの基本問題から入試標準レベルの問題まで幅広く収録されていますが、基本問題の割合が大きいです。
中堅国公立や中堅私大を目指す人には十分な一方で、よりレベルの高い大学を目指す生徒にとっては不十分と言えるでしょう。
そういった人は、本書の「実践問題」「総合問題」に取り組んだ後に、より難易度の高い問題集に取り組む必要があります。その際、おすすめの問題集を、セミナー化学の後におすすめの参考書でまとめているので参考にしてみてください。
解説がやや簡素である
解説がやや簡素であることも本書の弱みの一つです。教科書で習う範囲の問題を網羅的に収録している分、解答解説がコンパクトにまとめられてしまっています。
特に発展例題/発展問題において、公式を使う背景にある条件やなぜその解法なのかが省かれており、化学が苦手な人にとっては、解答解説だけで完璧に理解するのは難しいでしょう。
そういった人は、セミナー化学と併用するのがおすすめの参考書で紹介している解説本などを活用してみてください。
『セミナー化学』の使い方
ここからは、『セミナー化学』の正しい使い方を紹介します。
STEP1:授業の進度に合わせて発展問題を含めて1周する
まずは、授業の進度に合わせて発展問題を含めて1周してください。授業で習った範囲のプロセスやドリルを進めていき、定期テスト前に基本例題〜発展問題まで取り組むのが本書の基本的な使い方です。
発展例題/発展問題の難易度は高いですが、入試問題への橋渡しとなる問題ばかりなので、こちらも取り組みましょう。この時、できなかった問題には「必ず」印をつけておいてください。
STEP2:間違えた問題を2〜3周する
発展問題まで1周したら、STEP1で印をつけた問題を何もみずにできるまで復習してください。基本問題や発展問題では、実践問題/総合問題の土台となる典型的な解法を学べます。
これらをおろそかにしているとより発展的な入試問題に太刀打ちできなくなるので、必ずマスターしましょう。その際、以下の手順で進めていくのがおすすめです。
- 印のついた問題の解答解説を読む
- 知らなかった知識や解法を明確にする
- 何もみずにもう一度解く
- 模試前に何もみずに解けるか再確認する
STEP3:実践問題/総合問題にも取り組む
発展問題の復習まで終わったら、実践問題/総合問題にも取り組みましょう。入試基礎〜標準レベルの問題が収録されているので、初めのうちは解けない問題も多いはずです。
5分考えてもわからないときは、その問題に必要な解法や知識を知らない場合が多いのですぐに解答解説をみましょう。
ここで、解答の丸暗記をするのではなく、知識の暗記と解法の理解に分けることを意識してください。そうすることで、一つ一つの公式や現象を体系的に整理しながら学習できます。
この方法は、特に理論分野で効果的なのでぜひ参考にしてください。
『セミナー化学』で1問にかける時間
セミナー化学で問題演習を進める際、時間配分を意識して取り組むことが重要です。問題数が多いため、1問1問にじっくり取り組んでいたのでは完成までに時間がかかりすぎるからです。
以下のように、1問にかける時間を問題のレベル別にまとめたので参考にしてみてください。
プロセス/ドリル:1分
これらの問題はとにかくスピードを意識して取り組みましょう。最終的に、問題を見て反射的に答えが出るようになると良いです。
基本例題/基本問題:5分
こちらもスピードを意識して取り組みましょう。問題を見てすぐに解法が頭に浮かぶことを目標としましょう。
発展例題/発展問題:10分
入試基礎レベルな問題ばかりなので、この時間で解けると良いです。この問題がわからないときは、基礎的な理解が不足している場合が多いので、基本例題/基本問題に立ち返って復習しましょう。
実践問題/総合問題:10〜15分
入試標準レベルの問題も一部含まれているので、基本問題よりも時間をかけて取り組みましょう。5分考えてもわからない問題は、すぐに解答解説を見て解法を知るのが大切です。
『セミナー化学』に関する注意点
ここでは、本書に取り組む時の注意点を紹介します。
この注意点を見ておかないと、自分にあっていない参考書で効率の悪い勉強をしてしまう可能性が高いです。
以下の点に気をつけましょう。
発展問題まで取り組む必要がある
本書の最大の注意点は、発展問題まで解く必要があることです。本書の発展問題は、単元を習いたての時に解こうとしても難しく感じられ、飛ばしてしまう人も多い印象です。
しかし、発展問題は入試問題の典型的な解法パターンを学べる問題ばかりなので、飛ばすのはおすすめできません。解答解説や他の講義本を見ながらでもいいので取り組んでください。
発展問題を完璧にして初めて「セミナー化学をやり切った」と言えるので、手を抜かずに取り組みましょう。
より難しい参考書に取り組む必要がある
本書の注意点として、志望校レベルによってはより難しい参考書が必要であることも挙げられます。特に、関関同立やGMARCH以上の私大や国公立大を志望する受験生は、過去問演習の前に別の問題集を挟む必要があるでしょう。
本書に収録されている問題だけでは、入試問題に対応できません。例えば、難易度の高い有機合成や理論計算の問題など、演習量で差がつく問題に対して、セミナー化学の問題だけでは演習量が足りないでしょう。
志望校レベルに合わせて、重要問題集や良問問題集などの入試標準レベルの演習ができる問題集を活用してください。
受験期までに仕上げておく必要がある
本書に取り組む際、受験期までに仕上げておく必要があることに注意してください。
本書は、入試基礎〜標準レベルの問題が収録されており、本書だけでは入試問題に太刀打ちできる学力は身につきません。過去問演習やよりレベルの高い参考書での演習に必ず取り組む必要があります。
また、他の教科も学習するのを考えると、本書を仕上げるのにも少なくとも2〜3ヶ月は必要でしょう。そのため、本格的な受験勉強に入るまでに仕上げておきたい一冊です。
具体的には、以下のレベル別おすすめ学習時期を参考にして進めていってください。(再喝)
- 産近甲龍、日東駒専:高校3年の10月
- 関関同立、GMARCH:高校3年の7〜8月
- 早慶、旧帝大:高校2年の3月
- 東京一工:高校2年の12〜1月
『セミナー化学』の併用するのがおすすめの参考書
ここからは『セミナー化学』と併用すると効果的な、おすすめの参考書を解説していきます。
宇宙一わかりやすい高校化学
宇宙一わかりやすいシリーズの化学版で、語り口調でわかりやすく解説されているのが特徴的です。セミナー化学は問題演習に特化した教材のため、解説がやや簡素な傾向があります。
化学が本当に苦手な人にとって、特に熱化学や化学平衡など、化学反応の背景にある原理や原則を理解するのは難しいでしょう。本書では、ミクロな世界では何が起きているのかがわかりやすく解説されており、直感的に理解できます。
セミナーを解いていて、基本例題や基本問題の時点でもわからない時は、本書を使って基礎的な概念から復習してみるのがおすすめです。
『セミナー化学』の後におすすめの参考書
本書を終えた人は、過去問演習やより難易度の高い問題が収録されている参考書に取り組んでください。
具体的には、以下の『化学の良問問題集』、『化学の重要問題集』、『共通テストの過去問』の3冊がおすすめです。
化学の良問問題集
入試標準レベルの良問を集めた問題集です。重要問題集が網羅性に特化しているのに対して、本書は問題の質に特化しており、厳選された良問だけを周回したい人にはおすすめの問題集と言えます。
セミナー化学を終えてから本書に取り組むことで、ほとんどの難関大学の入試問題に対応できる学力を身につけられるでしょう。
化学の重要問題集
入試標準レベルの典型問題を網羅している問題集です。国公立大学で頻出の問題が揃っており、本書をやり込めば旧帝レベルの問題でも合格点を出せる学力を身につけられるでしょう。
特に、B問題ではセミナー化学のちょうどワンランク上の問題が収録されており、セミナーでは対応できない難関大学の問題に挑戦できます。早慶や旧帝以上レベルの大学を目指す生徒にとって、マストな問題集と言えるでしょう。
共通テストの過去問
国公立大学を志望する生徒は、セミナー化学の後に共通テストの過去問にも取り組みましょう。セミナー化学の各章末にも「共通テスト対策問題」が収録されていますが、それだけでは不十分です。
実際の過去問に触れることで問題の傾向や時間配分がわかるでしょう。特に共通テストは、センター試験に比べて問題文に癖があるので個別の対策が必須です。
『セミナー化学』についてのよくある質問
ここからは、本書について受験生からよく質問される点について答えていきます。
何周するべきですか?
基本的には1周で、できなかった問題だけ2〜3周するべきでしょう。本書の問題数は全部で1000問以上あり、全ての問題を2〜3周するのは時間がかかりすぎて効率が悪いからです。
セミナー化学の使い方で解説したように、まずは全ての問題を1周した後に間違えた問題だけを復習していきましょう。1周目に、間違えた問題に印をつけておくと、模試前や定期テスト前に印のついた問題をざっと復習できるので効果的です。
セミナー化学だけで共通テストは解けますか?
結論、6割までは解けるでしょう。それ以上を目指すのであれば、過去問での対策が必要です。
本書は、出題形式を模した「共通テスト対策問題」を活用して対策は可能ですが、共通テスト特有の問題の傾向や選択肢のややこしさには注意が必要です。
7〜8割以上を目指すには、これらへの対応が不可欠です。そのためには慣れが必要なので、セミナー化学を終えた後には必ず過去問演習に取り組んでください。