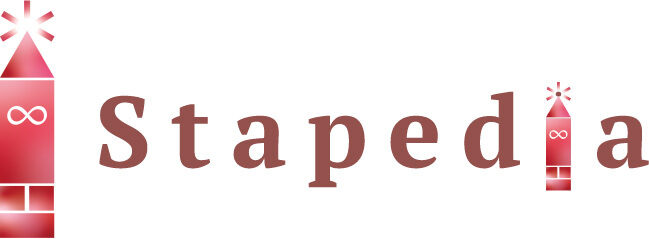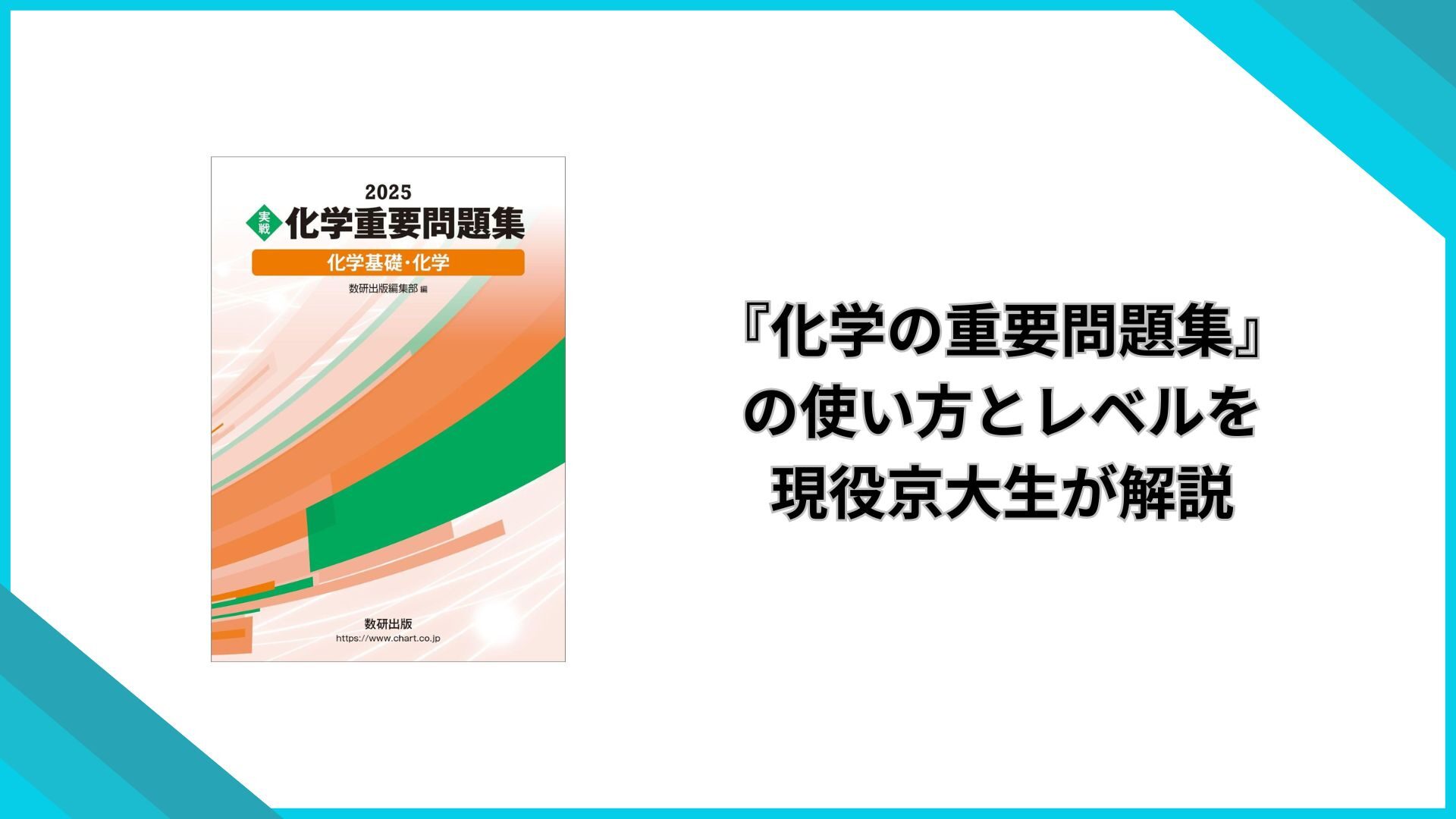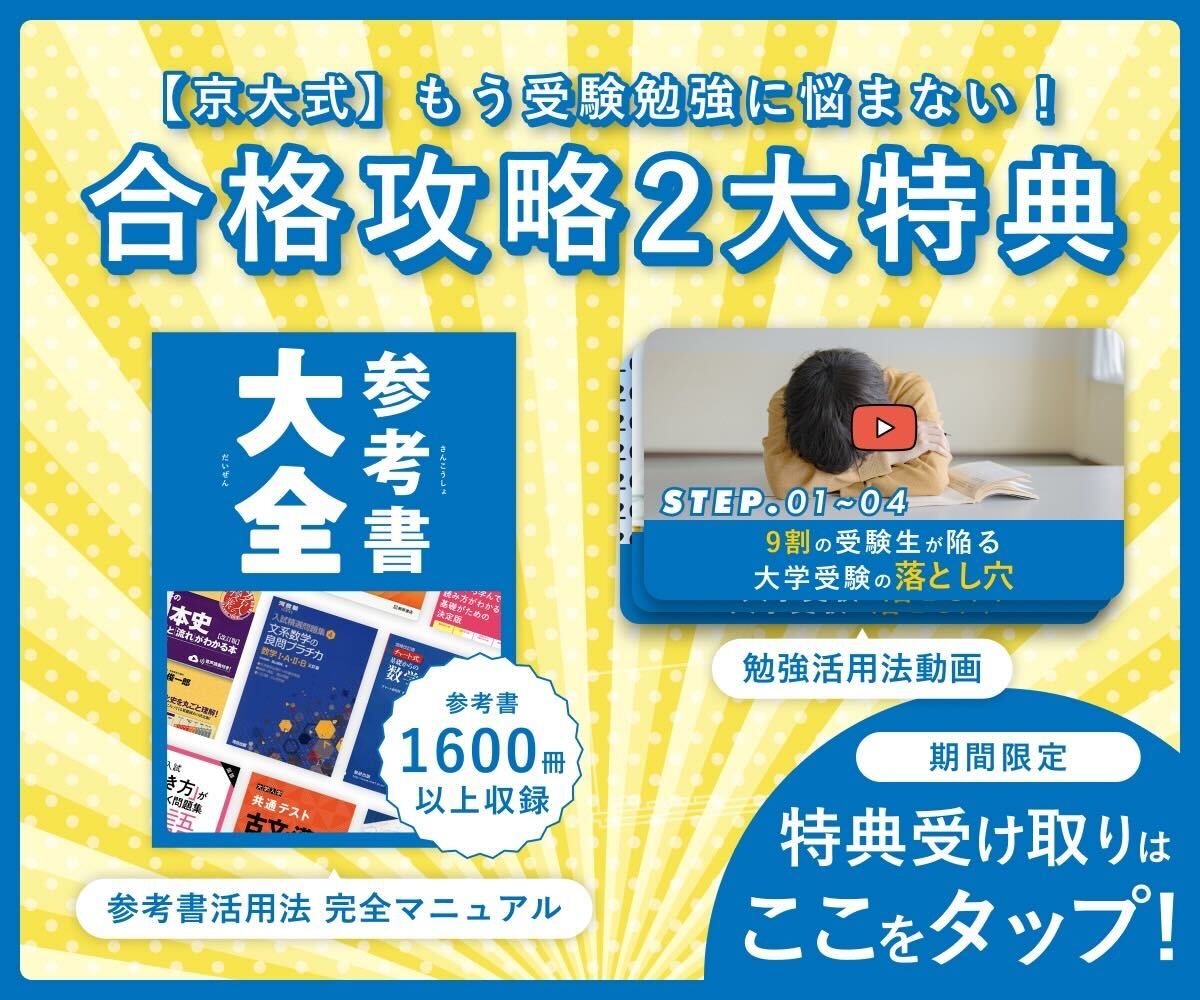『化学の重要問題集』は、数研出版が出版している網羅系の問題集です。
「要項」「A問題」「B問題」の3段階構成で入試における典型問題が幅広く収録されており、本書一冊で入試に向けた解法や思考力を身につけられる参考書になっています。
ただ、『化学の重要問題集』が自分の志望大学のレベルに合っているのか、自分の使い方で本当に学習効果があるのかを見極めるのは難しいですよね。
この記事では、『化学の重要問題集』の問題の難易度や到達できる大学のレベル、効果的な使い方などを解説します。本の具体的な内容や問題の難易度を理解して、適切な参考書選びができるようになることを目指しましょう。
この記事を書いた人
『化学の重要問題集』の商品情報
『化学の重要問題集』の基本情報です。
| 価格 | 935円 |
| 科目 | 化学 |
| 出版社 | 数研出版 |
| 目的 | 化学の入試標準レベルを習得し、さらに応用レベルの問題で演習を行う |
| 対象ユーザー | 化学の入試標準〜応用を学びたい人 |
| レベル | 〜早慶、旧帝大レベル |
| 難易度 | 普通〜やや難しい |
| 特徴 | 本書は、化学の全範囲について網羅された典型的な入試問題をA問題、B問題と段階的に学べる一方で、解説がわかりにくく基礎固めに向いていないという欠点もあります。 |
『化学の重要問題集』のレベル
本書を極めることで早慶や旧帝大レベルの問題まで解けるようになります。
これはB問題まで完璧にした場合ですが、A問題を完璧にするだけでもGMARCHや地方国公立レベルの入試では十分戦えるでしょう。
『化学の重要問題集』で到達できる偏差値
本書のA問題で到達できる偏差値は57.5〜62.5、B問題で到達できる偏差値は62.5〜67.5です。
自分の志望する大学の偏差値に合わせて、
- A問題のみ解く
- A問題と部分的にB問題も解く
- A問題もB問題も全て解く
のどれかを選択すると良いでしょう。
『化学の重要問題集』の強み
『化学の重要問題集』を他の参考書と比べた強みを紹介していきます。
化学の全範囲を網羅している
本書の最大の強みは、化学の全範囲を網羅していることです。
理論、無機、有機の各分野について、全国の入試問題から精選された問題が幅広く収録されています。
特に、理論分野ではA問題、B問題ともに良問が充実しており、これらの問題を完璧に理解することでほとんどの大学の入試問題に対応できるようになるでしょう。
入試の典型的な問題を網羅している
入試における典型的な入試問題が網羅されているのも本書の強みと言えるでしょう。
A問題では174問、B問題では87問収録されており、ほとんどの問題パターンを網羅できます。
特に、有機分野ではどれだけ典型問題をやりこんだかで点数に差がつくので、入試によくでる問題形式に対応できるようにしておきましょう。
A問題、B問題に分けられている
問題が難易度ごとにA問題、B問題と分けられているのも強みの一つです。
A問題では、GMARCHや地方国公立レベルの入試頻出問題が中心に収録されており、入試における標準的な解法や知識をマスターできるでしょう。
B問題では、早慶や旧帝大レベルの難問が収録されており、応用力を身につけられます。
注意点として、A問題でも入試レベルの問題なので、基礎固めを終えてから取り組みましょう。
『化学の重要問題集』の弱み
『化学の重要問題集』を他参考書と比べた弱みを紹介していきます。
基礎固めには向いていない
本書の弱みとして、基礎固めには向いていないことが挙げられます。
本書に収録されているのはあくまで入試標準〜応用の問題で、基本事項の確認問題は収録されていません。
各単元の冒頭に、「要項」として基本的な知識が整理されているものの基礎固めに十分とは言えないので、セミナー化学やリードαなどの問題集で基礎知識や計算方法をマスターしましょう。
化学が苦手な人には解説がわかりにくい
解説がわかりにくいのも本書の弱みの一つです。
本書には、本冊以上のページ数がある別冊解答が付属していますが、B問題のうち難問の解説がハイレベルで、化学が苦手な人にとっては理解しづらい可能性があります。
特に、難問揃いの理論分野において、立式までの発想のプロセスが読み取りにくかったり、途中の計算過程が簡潔すぎたりするので注意が必要でしょう。
そういった場合は、時間をかけて悩むよりも学校の先生や得意な友人に聞くことをおすすめします。
問題数が多い
問題数が多いことも本書の弱みと言えるでしょう。
2020年版では275問収録されており、これらの問題を全て理解し解けるようになるまでには相応の時間と労力がかかります。
じっくり時間をかけて完成させるのが理想的ですが、時間がない受験生はA問題だけに絞ったり、大学の頻出分野に絞ったりするなど自分に必要な部分を優先的に学習していきましょう。
『化学の重要問題集』の使い方
ここからは、『化学の重要問題集』の正しい使い方を紹介します。
STEP1:他参考書や「要項」を用いて基礎固めをする
本書に取り組む前に、まずは教科書や学校配布の問題集で一通り基礎固めをしてください。
そして、本書の「要項」を見て要点を全て理解していることを確認してから問題演習に取り組みましょう。
この時点で、知らない項目があれば教科書に戻って復習すると良いです。
STEP2:A問題を完璧にする
まずはA問題を完璧にすることを目標としましょう。
A問題を一通り全て解くことで、全単元の頻出パターンを網羅でき、入試標準レベルの問題への対応力が身につきます。
A問題では、全ての問題を解けるようにするために、以下の手順で進めると良いでしょう。
- 一単元ごとにA問題を全て解く
- 間違えた問題に印をつける
- 印をつけた問題を解説を意識しながら復習する
- 一単元終わったら次の単元へ
- 最後の単元まで終わったら最初の単元から2周目へ
注意点として、問題が解けても印を消さずに、蓄積していくのが大切です。
一度解けても再度間違えた問題には印がたまっていき、自分の苦手とする反応や問題設定を把握できます。
STEP3:B問題に着手する
早慶や旧帝大を志望する受験生は、A問題を完璧にしたのち、B問題に着手しましょう。
B問題では、応用力が求められる難問揃いなので、解く過程でつまづいたら一旦教科書やA問題に立ち戻って知識や解法を再確認するのが大切です。
『化学の重要問題集』で1問にかける時間
本書で1問にかける時間は、問題のレベルによって異なります。以下を参考にしてください。
・A問題:10〜15分
A問題では、ケアレスミスに注意しながらスピードを意識して解きましょう。
A問題が解けない場合は、知識が不足している可能性が高いので、すぐに解答を見ることをおすすめします。
・B問題:20〜25分
B問題では、入試本番を想定してじっくり考えることで思考力を鍛えましょう。
問題が解けなくてもすぐには解答を見ないで、見落としている条件はないか、ヒントとなる反応はないかを吟味することが大切です。
それでもわからないときは、解説を熟読し、立式に至る発想のプロセスを読み取ることが重要です。
これらを目安にして進めていき、2〜3周目にはより早く解けるように解説を確実に理解しましょう。
『化学の重要問題集』に関する注意点
ここでは、本書に取り組む時の注意点を紹介します。
この注意点を見ておかないと、自分にあっていない参考書で効率の悪い勉強をしてしまう可能性が高いです。
以下の点に気をつけましょう。
基礎が固まる前に手を出してはいけない
基礎が固まる前に本書に手を出してしまうと、知識や解法の暗記に終始してしまい、思考力が身につかないので注意が必要です。
化学は物理や数学に比べて暗記項目が多く、そもそも覚えてないと解けない問題もあるので、知識の暗記→基本問題→応用問題と段階的に学習していくことが重要です。
本書に取り組む前にまずは、学校配布の問題集で基本的な知識をインプットしていきましょう。
完璧にやりきろうとしてはいけない
本書に取り組む時には、完璧にやりきることに固執しないように注意してください。
本書では、全275問(2020年版)が収録されており、全ての問題を完璧に理解するのは容易ではありません。
自分の志望大学では解けなくてもいい問題まで取り組んで時間を浪費してしまうのは非常にもったいないです。
GMARCHや地方国公立志望の受験生であれば、A問題を完璧にするので十分です。
本書を”完遂”すること自体を目的にしないように注意しましょう。
「皆が使っている」という理由で手を出してはいけない
「有名だから」「周りがやっているから」という安易な理由だけで、本書に手を出すのは厳禁です。
本書は多くの受験生が使用する定番の参考書ではありますが、イコール自分に最適とは限りません。
特に、基礎が固まる前に始めてしまうと挫折する可能性が高く、非効率です。
基礎固めを確実にしてから本書に取り組み始めましょう。
『化学の重要問題集』の前におすすめの参考書
ここからは『化学の重要問題集』の前に使うと効果的な、おすすめの参考書を解説していきます。
セミナー化学
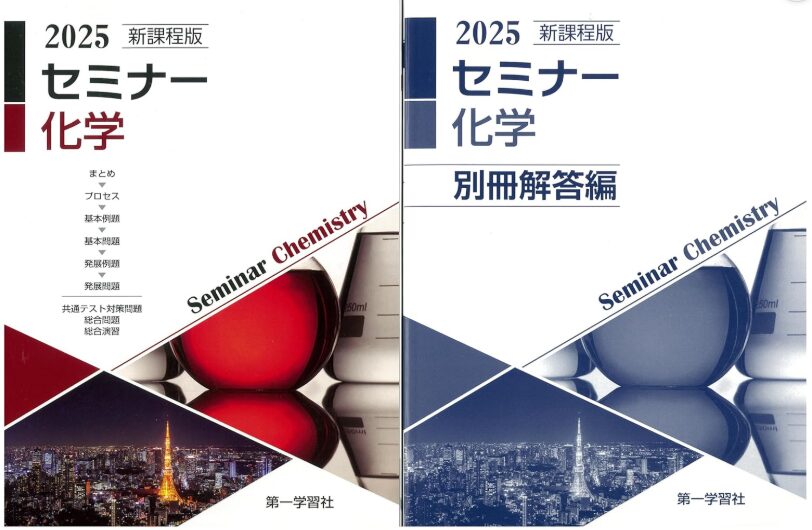
基礎固め向け教科書傍用問題集です。
化学の基礎事項を幅広くカバーしており、例題で基本的な知識を、練習問題で計算方法をマスターできます。
『化学の重要問題集』に取り組む前に、まずはこのレベルの問題が8割以上解けることを目標にしましょう。
本書は筆者も受験生時代に使っており、『重要問題集』の土台として練習問題を回していました。
リードα
基本的な教科書傍用問題集で、内容や使い方はセミナー化学と同じです。
セミナー化学と異なる点として、章ごとに基本事項が整理されており化学が苦手な人に特におすすめの一冊です。
本書で頻出問題の計算パターンを頭に入れておくとスムーズに『化学の重要問題集』に取り組めるでしょう。
鎌田の講義シリーズ
学校の授業だけでは完全に理解できない人におすすめの参考書です。
問題に出てくる現象の根底にある理論が、非常に丁寧に解説されており、問題集の解説を見ても理解できない時に有効です。
自分の苦手な分野の講義本を一冊持っておくだけでも、人に聞く手間が省けるので、学習効率が改善するでしょう。
『化学の重要問題集』の後におすすめの参考書
本書を終えた人は、過去問演習やより難易度の高い問題が収録されている参考書に取り組みましょう。
具体的には、以下の『志望大学の赤本』、『化学の新演習』の2冊がおすすめです。
志望大学の赤本
ほとんどの受験生は重要問題集を終えたら、志望校の過去問演習に取り組みましょう。
実際の入試問題に触れることで、志望大学の出題傾向や問題形式の癖を知ることができます。
この時、時間配分や答案作成を意識しながら何年分も解くことで、受験本番に落ち着いて取り組めるでしょう。筆者は、各科目について最低でも7年分の過去問は解いていました。
化学の新演習
医学部志望や旧帝大の中でも東大京大を志望する受験生は、過去問演習の前に本書に挑戦するのも良いでしょう。
本書は、『化学の重要問題集』のB問題よりもハイレベルな問題が多数収録されており、非常にやりごたえのある一冊です。
ただ、重要問題集をやり終えても物足りない人向けなので、時間がない場合はスルーしても問題ありません。
『化学の重要問題集』についてのよくある質問
ここからは、本書について受験生からよく質問される点について答えていきます。
A問題だけやるのでもいいですか?
志望大学のレベルによってはOKです。
例えば、GMARCHや関関同立志望の人は入試標準レベルの問題を解ければ良いので、A問題を仕上げるだけでも十分に戦えるでしょう。
一方で、それ以上の難関私大や難関国公立志望の受験生は、B問題も解けるようになる必要があります。
A問題で入試標準レベルの土台を固めた後に、B問題でより応用的な思考力を鍛えていきましょう。
受験生はいつから始めるべきですか?
高3の夏前から始めるのが理想的です。
それまでに基礎的な知識や計算方法をマスターしておくと、夏休みに本書を極められるので、秋以降の共テ対策や冬以降の過去問演習にスムーズに取りかかれます。
実際に、筆者の周りの京大志望の受験生は、9月の時点で重要問題集を2周は終えてました。
いきなり重要問題集に手を出しても大丈夫ですか?
結論、おすすめできません。
本書は基礎力がある前提の構成なので、現時点で入試標準レベルの問題が解ける実力がなければ、オーバーワークになる可能性が高いです。
教科書傍用問題集で発展問題を含めて8割以上解けるようになるまでは、手を出さない方がベターです。