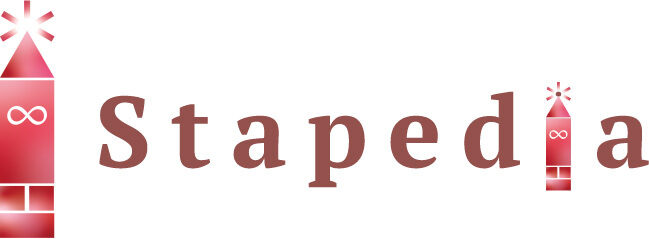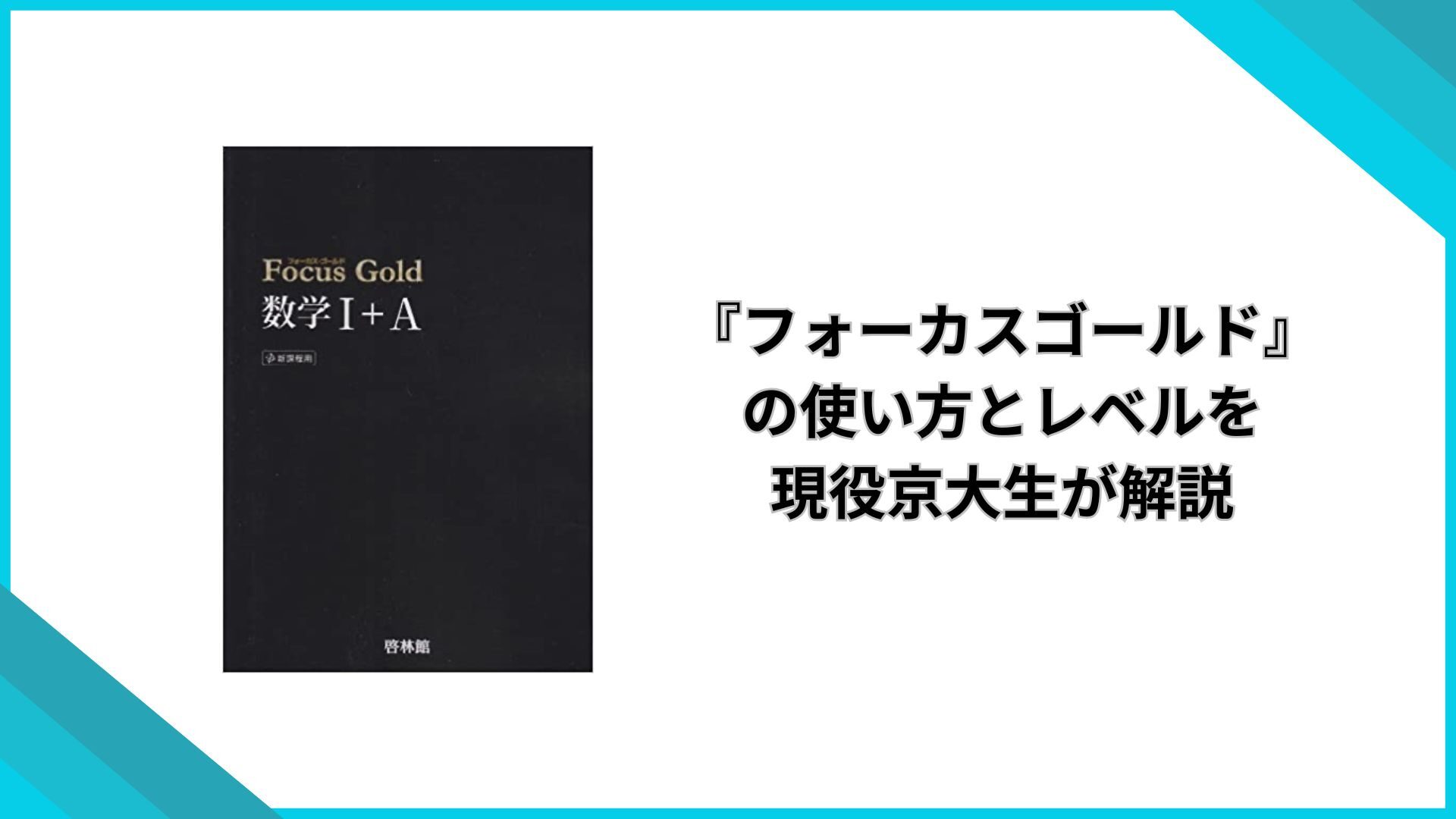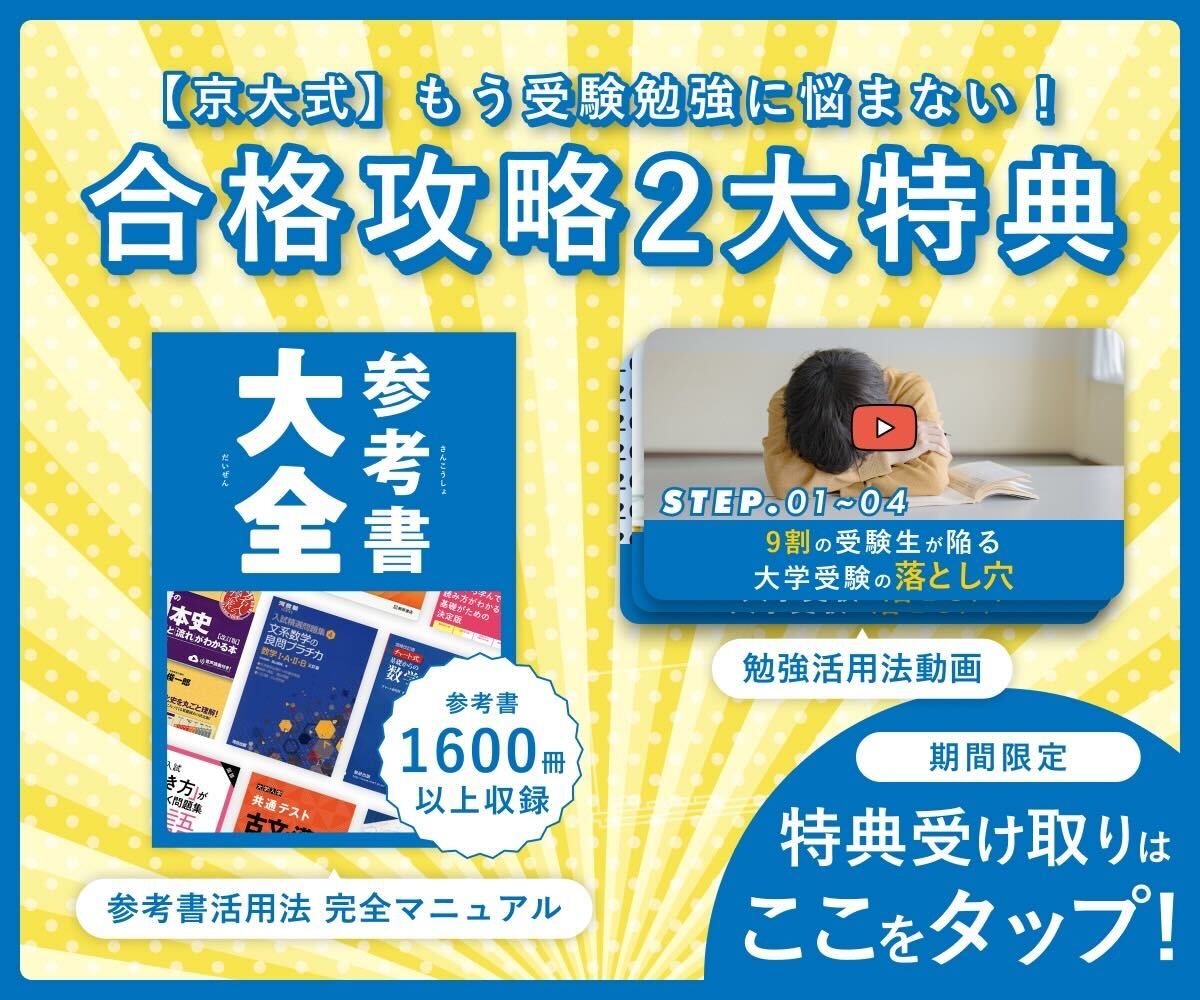『フォーカスゴールド』は、啓林館が出版している網羅系の問題集です。基礎〜応用まで6段階構成で幅広い問題が収録されており、解説も非常に丁寧でわかりやすいので、数学が苦手な人でも手に取りやすい参考書になっています。
ただ、『フォーカスゴールド』が自分の志望大学のレベルに合っているのか、自分の使い方で本当に学習効果があるのかを見極めるのは難しいですよね。
この記事では、『フォーカスゴールド』の問題の難易度や志望大学レベル、効果的な使い方などを解説します。本の具体的な内容や問題の難易度を理解して、適切な参考書選びができるようになることを目指しましょう。
この記事を書いた人
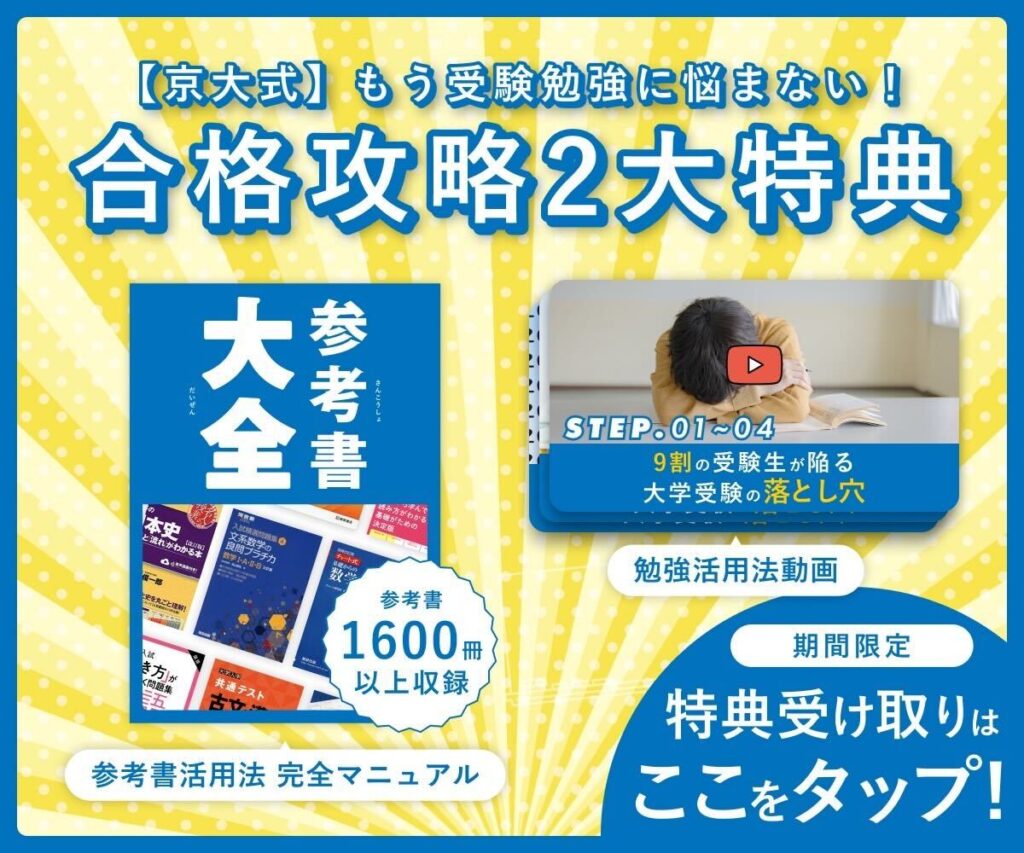
『フォーカスゴールド』の商品情報
『フォーカスゴールド』の基本情報です。
| 価格 | 2,070円(数学1+A) 2,500円(数学2+B+ベクトル) 2,600円(数学3+複素数平面・式と曲線) |
| 科目 | 数学 |
| 出版社 | 新興出版社啓林館 |
| 目的 | 大学入試に必要な解法をインプットする。 |
| 対象ユーザー | 数学を勉強するあらゆるレベルの受験生 |
| レベル | 〜旧帝大 |
| 難易度 | 普通〜難しい |
| 特徴 | 本書はあらゆるレベルの問題を網羅しながらも解説も丁寧で、数学の成績を上げたい全高校生にとって役立つ一冊ですが、問題数が非常に多く、章末問題のレベルが高すぎるという欠点もあります。 |
『フォーカスゴールド』の難易度
本書の難易度は、”普通〜難しい”です。
教科書レベルの基礎問題も収録されていますが、「Step up」の章では、最難関私大や難関国公立レベルの問題もあります。
各問題の難易度は、以下を参考にすると良いでしょう。
・check!
教科書レベルの計算問題で、全ての問題の基礎となる計算能力を養えます。
問題をみた瞬間に答えを出せるようになってください。
・星1.2問題
GMARCHなど難関私大の小問(1)で問われるようなレベルの基本問題で、受験数学の基礎的な解法を身につけられます。
問題を見たらすぐに解法が浮かぶようになるまで、周回してください。
・星3.4問題
難関大学の入試で問われやすい典型問題で、これらの標準的な解法を身につけることで、より応用的な解法を積み上げる下地ができます。
これらの問題を瞬殺できるようになれば、早慶や旧帝レベルの問題にも対応できるようになってきます。
このように本書は、非常に幅広いレベルの受験生に対応した参考書となっており、数学を勉強するあらゆる受験生にとって有用でしょう。
『フォーカスゴールド』で到達できる偏差値
本書を極めることで、偏差値70まで到達可能です。
収録されている星1〜4の問題の解法をすべてインプットすることで、文系であれば旧帝レベル、理系であれば最難関私大のレベルまで到達できるでしょう。
『フォーカスゴールド』の強み
『フォーカスゴールド』を他の参考書と比べた強みを紹介していきます。
網羅的に収録されている
本書の最大の強みは、基礎から応用までのあらゆるレベルの問題が網羅され、最適な学習の流れとなるように6段階に分けて整理されていることです。
マスター編では入試でよく問われる重要度の高い問題が揃っており、さらにチャレンジ編では、実際の入試問題が丁寧に解説されていて、自身のレベルに合わせた学習ができるでしょう。
マスター編の問題を完成させるだけでも、入試に必要十分な解法は網羅できるので、大学の過去問を解いても全く手が出ないという状態から抜け出せます。
解説がわかりやすい
解説が非常にわかりやすいのも、本書の大きな強みです。
一般的に、網羅系の参考書では解説が簡素になりがちなところ、本書は一問一問に丁寧な解答解説が掲載されているので、学習者の理解を最大限高めてくれるでしょう。
また、より詳しい解説が載っている別冊解答編と3種類のコラムが理解を最大限サポートしてくれるので、数学の成績を上げたい全ての高校生にとって役立つ一冊です。
基礎知識の「まとめ」が優秀
本書の強みとして、章末に基礎知識の「まとめ」があることも挙げられます。
本書に付属している公式集とセットで使うとさらに効果が高く、公式を一通り覚えた後に、一つ一つの公式がどのように関連しているのかを整理できるでしょう。
学習してきた知識や解法を体系的に整理することで、小手先の得点力ではなく本質的な理解が身につきます。
『フォーカスゴールド』の弱み
『フォーカスゴールド』を他参考書と比べた弱みを紹介していきます。
章末問題の難易度が高すぎる
本書の弱みとして、「Step up」問題や章末問題の難易度が非常に高いことが挙げられるでしょう。
これらの問題は、最難関私大や旧帝大志望でも全てを完答するのは難しく、ほとんどの受験生にとってオーバーワークになってしまう可能性が高いです。
自分の志望する大学のレベルを越えた問題を捨てる選択も、最短ルートで合格するためには大切です。
図形や整数の問題と相性が悪い
図形や整数の問題と相性が悪いのも本書の弱みの一つでしょう。
本書は、パターン暗記が重要な数1、数2BC、数3には効果的な一方で、図形や整数といった試行錯誤を重ねながら解答に辿り着ける分野とは相性が悪いです。
そういった分野では、一問に対してどれだけ考え抜いたかの方が重要で、パターン暗記にはあまり意味がありません。
これらの分野では、解法を一つ一つ個別で覚えるのではなく、一問一問に対して適応できる解法はないかを洗い出していく癖を身につけると良いでしょう。
完成までやり切るのが難しい
完成までやり切る難易度の高さも本書の弱みです。
幅広いレベルの問題が収録されている反面、その問題数も他参考書と比べて段違いに多いです。
特に、数学2+Bは問題数910問と非常に多く、これら全ての問題を解くのは非常に難しいでしょう。
自分の志望する大学のレベルに合わせて、 難しすぎる問題をあえてやらない選択も必要です。
『フォーカスゴールド』の使い方
ここからは、『フォーカスゴールド』の正しい使い方を紹介します。
STEP1:1周目に解法のインプットを行う
本書の1周目は、解法のインプットを目標に以下の手順で進めていきましょう。
- 例題とその解答をみて解法を知る。すぐ下の練習問題を解く。
- わからなければすぐに解説をみて、解法を覚える。
- わからなかった問題に印をつけておく。
- 章ごとに印のついた問題を復習する。
- 1〜4を全ての章で行い、1周目を終える。
学習する順番について、それぞれの分野について最初から最後まで一気にやり切ってから次の分野に入るのがおすすめです。
その分野の様々な解法を体系的に学べるとともに、挫折しにくいというメリットがあります。
このとき、わからない問題があれば長時間考えずに積極的に解説を見てください。
インプットの段階で、解法を知らない問題を考え続けても時間の無駄なので、すぐに解説を見ると良いです。
STEP2:2,3周目に解けなかった問題を復習する
1周目を終えたら、次は印のついた練習問題を重点的に解いていきましょう。
その問題が解けたら印を消さずに、蓄積していくのが大切です。
一度解けても再度間違えた問題には印がたまっていき、自分の苦手とする問題の分野や条件設定を把握できるでしょう。
これによって、定期試験前や模試前に苦手問題を重点的に復習できるので効率が大変良いです。
注意点として、2〜3周目は数1A、数2BC、数3について1周目と同じ順番で進めていきましょう。
(例えば、一週目が数1A→数2BC→数3なら、2〜3周目もその順番)
こうすることで、復習間隔が均等にかつ十分に空き、学習効果を最大限高めてくれます。
長期記憶をするためには一度学習してから十分な時間をおく必要があるのは、エビングハウスの忘却曲線によっても明らかです。
STEP3:「Step up」問題にも取り組む
星1〜4の練習問題のほとんどの問題を完答できるようになった人は、「Step up」問題にも取り組みましょう。
ただし、全ての受験生が「Step up」問題をやる必要はなく、難関国公立の理系志望や医学部を志望する受験生のみで大丈夫です。
それ以外の人は、他教科の勉強や赤本に取り組んだ方が、合格に近づくでしょう。
『フォーカスゴールド』で1問にかける時間
本書の1問あたりにかける時間は、25分までを目安としてください。
理由は、東京大学の入試数学でも大問1問あたりの時間は25分であり、25分考えて解けない問題はそれ以上考えても解けない可能性が高いからです。
初見で解けなくても、2周、3周と繰り返して解けるようになれば良いので、一問に固執せず効率的に勉強していきましょう。
『フォーカスゴールド』に関する注意点
ここでは、本書に取り組む時の注意点を紹介します。
この注意点を見ておかないと、自分にあっていない参考書で効率の悪い勉強をしてしまう可能性が高いです。
以下の点に気をつけましょう。
完成までに時間がかかる
本書の一番の注意点として、全ての問題をやり切ろうとしてはいけないことです。
最難関私大志望の受験生でも、「Step up」の問題はオーバーワークになる可能性があり、星1〜4の問題の完成度を上げた方が得点力は身につくでしょう。
また、本書で解けない問題を捨てることで、入試本番で解けなくてもいい難問を見抜く力が養われ、解ける可能性の高い問題に注力できます。
自分の志望大学では、どのレベルの問題まで解けるようになるべきなのか意識しながら進めるのも大事ですよ。
志望大学に応じて問題を捨てる必要がある
完成までに時間がかかるのも本書に取り組む上での注意点です。
自分が解かなくても良い問題を除いたとしても、それ以外の問題を完璧に理解し完答できるようになるまでに相当な時間がかかります。
「Step up」と星4の問題をやらないと仮定しても、数1Aでは594問、数2BCでは738問、数3では574問もあり、1週間や2週間で完璧にするのは現実的ではありません。
高校3年生になって焦って詰め込む羽目になる前に、高校1〜2年生のうちから進めておくのが大切でしょう。
一対一対応の解答暗記に終始してはいけない
もうひとつ注意したいのが、解法暗記に終始してはいけないことです。
本書の解説があまりにも丁寧であるが故に、間違えた問題の解法を暗記しただけで終わってしまい、類題が出てきても解けない状態に陥ってしまう人が毎年発生します。
問題の解法を一つ一つ個別で暗記するのではなく、その類題にも適応できるように、解法をパターン化して暗記を心がけましょう。
例えば、「この問題はこの手順で解けるんだな。」で終わらせず、「この条件があるからこの解法を使うんだな。じゃあ、同じ設定の違う問題もこれで解けるな。」というように解法の抽象度を一段あげて理解すると良いです。
『フォーカスゴールド』の前におすすめの参考書
ここからは『フォーカスゴールド』の前に使うと効果的な、おすすめの参考書を解説していきます。
サクシード
『フォーカスゴールド』などの、網羅系参考書と同時並行で本書にも取り組むと良いでしょう。
網羅系参考書で理論を学びつつ、本書で計算能力を高めることで数学力を総合的に上げられます。
check問題や星1,2の問題と被るところもありますが、計算練習だと思って飛ばさずに解いていきましょう。
本書は、筆者の高校指定の参考書で、表紙がボロボロになるまで演習を積んだのを覚えています。
入門問題精講
『フォーカスゴールド』に入る前に不安がある人は、本書に取り組むと良いでしょう。
check問題〜星1,2レベルの問題が幅広く収録されており、内容は被りますが、基本問題の演習量を確保できるでしょう。
数学が極端に苦手な人以外は、本書をスキップしてokです。
やさしい高校数学
数学が極端に苦手な人におすすめしたい一冊です。
基本的な原理・原則が教科書よりもさらに丁寧に解説されているので、『フォーカスゴールド』に取り組むための最低限の理解を身につけられます。
『フォーカスゴールド』のcheck問題や星1でも苦戦する人は、この本を使って理解→演習→理解→演習と交互に進めていくとよいでしょう。
『フォーカスゴールド』の後におすすめの参考書
本書を終えた人は、過去問演習やより難易度の高い問題が収録されている参考書に取り組みましょう。
具体的には、以下の『志望大学の赤本』、『プラチカ』、『やさしい理系数学』の3冊がおすすめです。
志望大学の赤本
ほとんどの受験生は、 『フォーカスゴールド』の次に志望校の赤本に取り組むと良いでしょう。
それまで学んだ解法を組み合わせながら、時間内に完答する練習ができます。
解説を読んでもわからない時は、まず『フォーカスゴールド』に類題はないかチェックして、条件を見落としていたのか、条件からの立式ができなかったのか、など解けなかった原因を分析するのが大事です。
赤本に取り組む時のポイントとして、時間を計りながら解答を全て書くように意識して解きましょう。
本番を想定して何度も取り組むことで、当日の焦りや不安を軽減できるでしょう。
プラチカ
最難関私大や旧帝大の理系を志望する受験生は、過去問の前に本書を挟むのをおすすめします。
『フォーカスゴールド』のStep up問題よりもさらに難しい問題が収録されている一方で、解答部分がかなり分厚く非常に丁寧に解説されています。
志望校の過去問に向けて段階的にレベルを上げていくことで、オーバーワークになり学習効果が下がるのを防げるでしょう。
受験生時代、同じ大学を志望する仲間はこぞって本書を選んでいました。
やさしい理系数学
旧帝上位の理系志望や医学部志望の受験生で、数学を得点源にしたい人は本書に取り組むのも良いでしょう。
ただ、本書には大学入試を超える数学オリンピックレベルの問題も掲載されており、一般的な受験生が完成を目指すのは非現実的です。
この本を扱う際は、自身の大学に出てきそうな傾向の問題のみをピックアップして解くと良いでしょう。
『フォーカスゴールド』についてのよくある質問
ここからは、本書について受験生からよく質問される点について答えていきます。
青チャートやレジェンドと、どれを選べば良いですか?
結論、学校指定の問題集を進めていきましょう。
わざわざ本書を追加する必要はありません。
ただ、学校指定の問題集がフォーカスゴールドゼータや黄チャートで簡単すぎると感じる人や、そもそも学校指定がない人はフォーカスゴールドを選ぶと良いでしょう。
他2冊に比べて、
- 基本的な問題も掲載している
- 解説がより丁寧
という理由から本書をおすすめできます。
もし3冊の中でどれを選ぶべきか迷ったら、以下の表を参考にしてみても良いかもしれません。
| フォーカスゴールド | 青チャート | レジェンド | |
|---|---|---|---|
| 網羅性 | ◎(基本問題もある) | ◯ | ◯ |
| 解説の丁寧さ | ◎(視覚的にもわかりやすい) | ◯ | ◎(フォーカスゴールドと同様、 解説が丁寧) |
| 問題の質 | ◯ | ◎(良問が揃っている) | ◯ |
フォーカスゴールドは難しいですか?
本書の難易度は、”普通〜難しい”ですが、基礎から応用まで6段階に分けて構成されているため数学が苦手な人でも取り組めます。
そういった人は、まず教科書レベルのcheck問題から取り組み、終わったら星1〜3の問題を周回して、まずは基礎〜入試標準レベルの問題を完璧に仕上げることを目標にしましょう。
星4や「Step up」の問題は旧帝大レベルの問題となってくるので、ほとんどの人は飛ばしてokです。
一方で、これらの大学を目指す人は完答できるまで周回しましょう。
他の問題集と併用してもいいですか?
本書の解説だけでは理解できない人が、教科書や『やさしい高校数学』などの解説系の参考書と併用するのは問題ないです。
ただし、チャート式など他の網羅的参考書と併用するのはおすすめできません。
やるべき量が膨大になり、一問一問の理解度が下がるからです。
本書では、出版社が厳選した重要度の高い典型問題が、学習の流れを意識して整理されているので、それに則って学習を進めていくのが一番効果的でしょう。